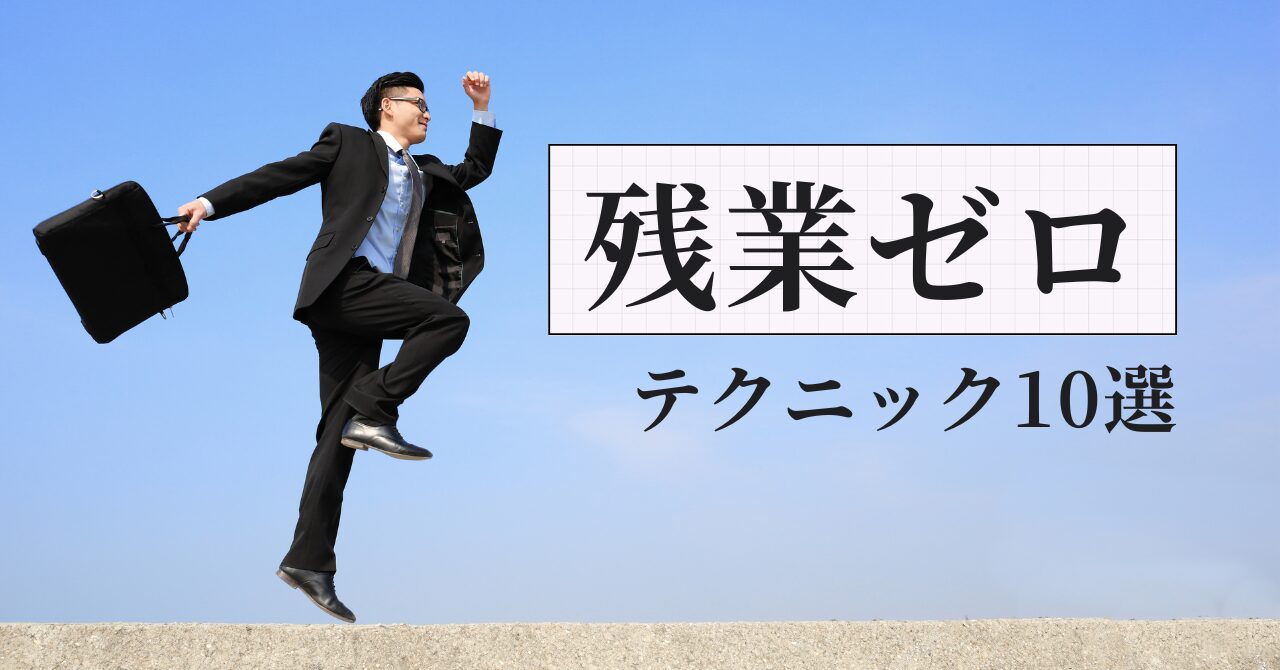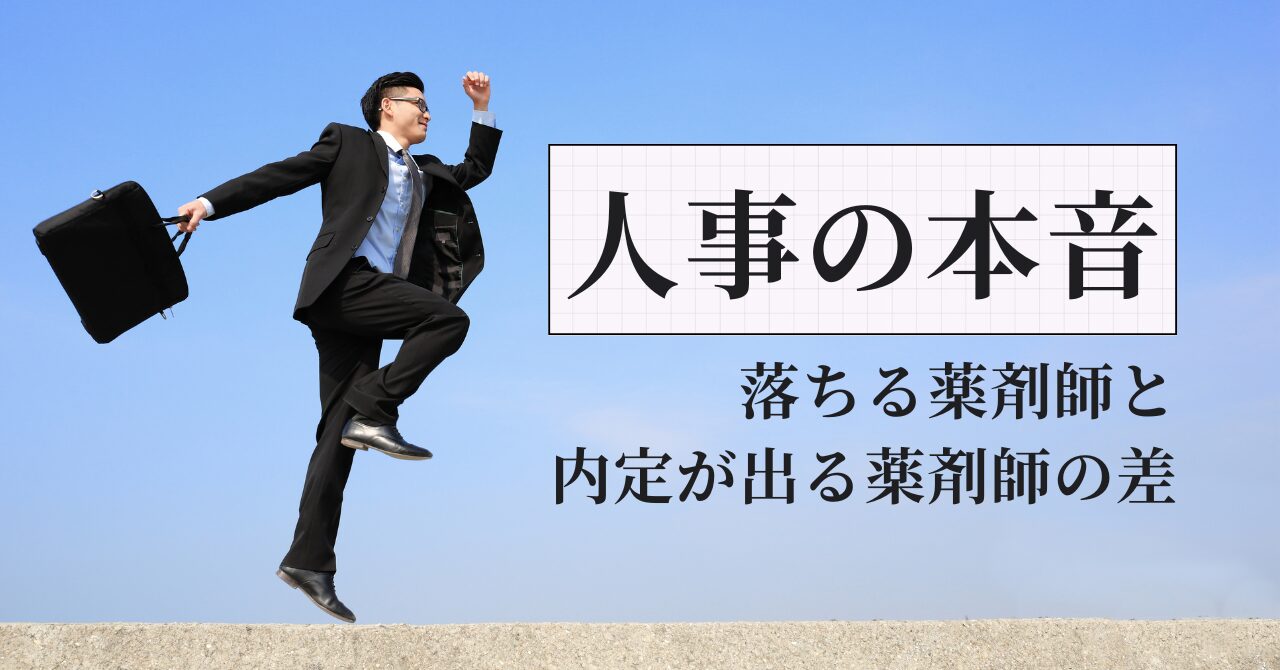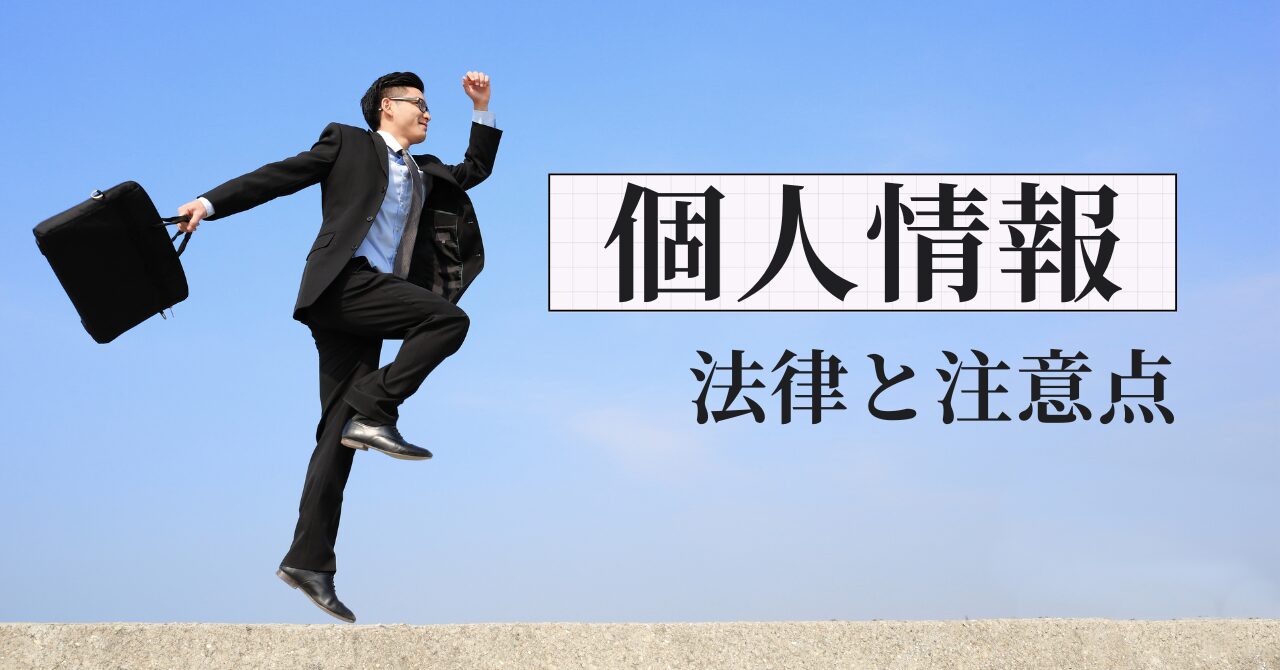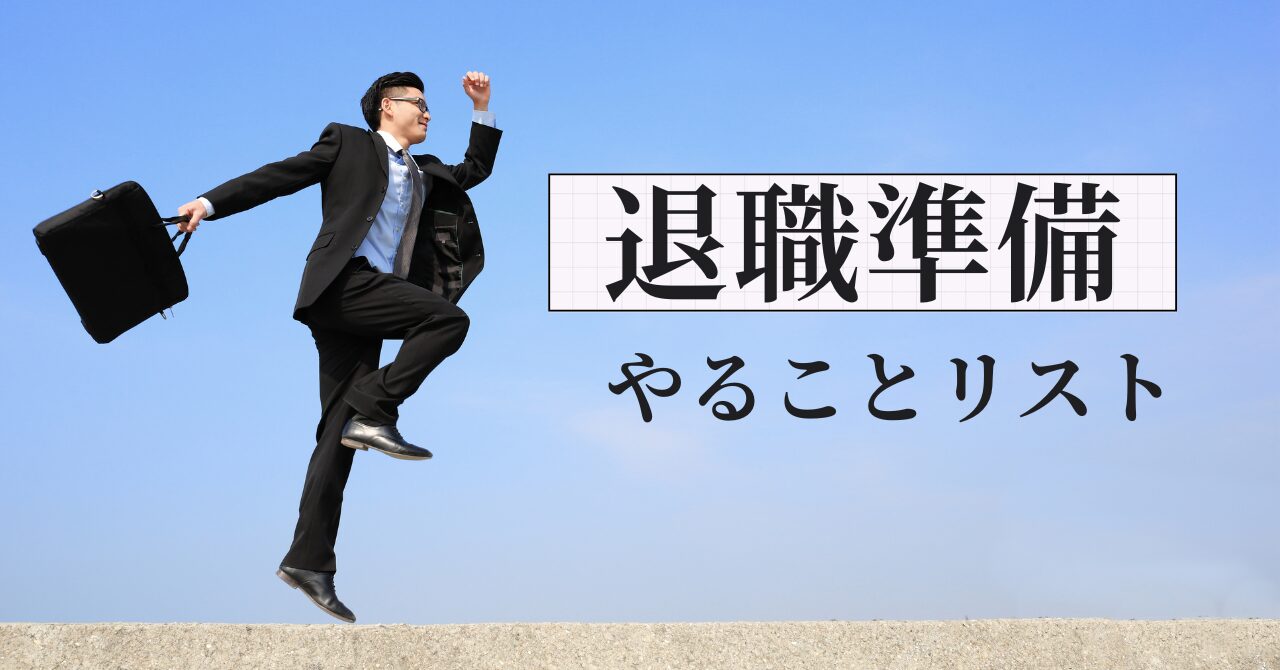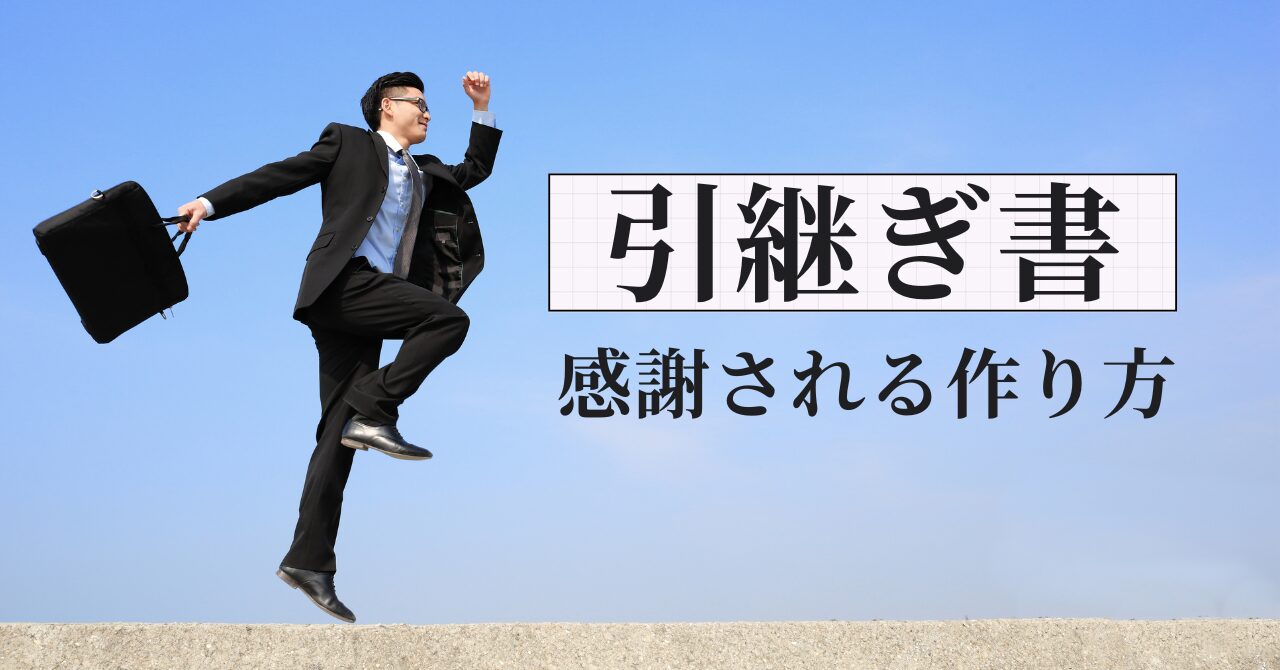2025年9月時点の情報です
知識は私の方があるのに、なぜあの人の方が評価されるの?
服薬指導の内容は完璧なのに、患者さんからの指名は別の薬剤師へ。
疑義照会で正論を伝えているのに、医師からは煙たがられる。
そして、同期や後輩の方が先に管理職に昇進していく。
もしあなたが今、こんな悔しさを感じているなら、原因は「知識不足」ではありません。「プレゼン力(伝え方)」で損をしているだけです。
私は調剤薬局チェーンで人事部長として、多くの薬剤師と面接してきました。その中で気づいたことがあります。専門知識は十分なのに、プレゼンテーション能力が低いために正当な評価を受けられない薬剤師が驚くほど多いのです。
厚生労働省の「患者のための薬局ビジョン」では、薬剤師に対人業務の強化が求められています。しかし現場では「説明が長い」「何が言いたいのか分からない」と患者や医師から不満の声が上がっているのが実態です。
実は、プレゼンテーション能力の差は年収にも直結します。運用していた人事評価制度では、同じ業務量でも「伝わる話し方(コンピテンシー評価)」の点数差により、昇給や管理職登用に差が生じるため、体感では年間数十万円程度の差が生じている印象でした。これは一企業の例に過ぎませんが、多くの薬局が「対人業務」を評価の軸に移している今、決して珍しい数字ではありません。
この記事では、元人事部長かつ薬剤師として、医師や他職種、患者に「伝わる」プレゼンテーション技術を具体的に解説します。明日からすぐ使える実践的なテクニックをお伝えしますので、最後までお読みください。
なぜ薬剤師のプレゼンテーション能力が注目されるのか
対人業務シフトで変わる薬剤師の役割
調剤報酬改定のたびに、対物業務から対人業務への移行が加速しています。かかりつけ薬剤師制度、服薬情報等提供料、在宅医療への参画。これらすべてに共通するのが「他職種や患者との円滑なコミュニケーション」です。
しかし多くの薬剤師は、大学で専門知識は学んでも、プレゼンテーション技術は教わっていません。結果として、知識はあるのに「伝え方」で損をしているのです。
私が人事部長だった頃、ある30代の薬剤師から相談を受けました。彼女は服薬指導に時間をかけ、丁寧に説明しているつもりでした。ところが患者満足度調査では「説明が分かりにくい」と評価され、昇給審査で落とされたのです。
医療現場で求められる「伝わる力」
医師や看護師との連携場面を想像してください。疑義照会で「この処方、相互作用が心配なんですが」と曖昧に伝えても、多忙な医師は取り合ってくれません。
「デパケン400mgとアスピリン併用で、遊離バルプロ酸濃度上昇のリスクがあります。過去に出血傾向の副作用報告があるため、減量をご検討いただけますか」と具体的に伝えれば、医師も納得して処方変更に応じます。
この差が「プレゼンテーション能力」なのです。
ポイント1:「結論ファースト」で医師の時間を奪わない技術
なぜ薬剤師の説明は長くなるのか
薬剤師の説明が長くなる最大の理由は「背景から話し始めるクセ」です。医師への疑義照会でも、患者への服薬指導でも、経緯や理由を先に述べてしまう。相手が求めているのは「結論」なのに、です。
私が面接で「当社を志望した理由は?」と聞くと、「実は前職の薬局では人間関係が悪くて、お局薬剤師に毎日嫌味を言われて、シフトも希望が通らず…」と延々と背景を語る応募者がいました。聞きたいのは「なぜ当社なのか」という結論です。
結論ファーストの実践方法
医療現場で使える「結論ファーストのフレームワーク」は以下の通りです。
【PREP法の活用】
- P(Point):結論を最初に述べる
- R(Reason):理由を説明する
- E(Example):具体例を示す
- P(Point):結論を再度強調する
具体例を見てみましょう。悪い例と良い例を比較します。
【悪い例】疑義照会での説明 「先生、今回の処方なんですけど、患者さんが前回別の病院でロキソニンをもらっていて、それで今回先生がボルタレンを出されたんですが、患者さんが腰痛で両方飲みたいと言っていて…」
【良い例】疑義照会での説明 「先生、ロキソニンとボルタレンの重複処方についてご確認です。理由は、患者さんが別医療機関で既にロキソニンを服用中だからです。NSAIDsの重複は消化管出血リスクを高めます。どちらかに統一していただけますか」
この差が分かりますか?良い例では30秒で要件が伝わります。医師の時間を奪わず、的確な判断を引き出せるのです。
服薬指導での結論ファースト
患者への服薬指導でも同じです。高齢者や忙しい社会人に、長々と説明しても記憶に残りません。
【悪い例】服薬指導 「この薬はですね、血圧を下げる薬でして、朝食後に飲んでいただくんですが、飲み忘れた場合は次の服用時間が近い場合は1回飛ばして、でも血圧が高い状態が続くと良くないので…」
【良い例】服薬指導 「この薬は血圧を下げます。毎朝食後、1錠飲んでください。飲み忘れたら、次の時間まで6時間以上あれば気づいた時に飲んでください。6時間未満なら1回飛ばしてください」
シンプルで明確。これが伝わるプレゼンテーションです。
ポイント2:専門用語を「翻訳」する技術が患者の信頼を生む
専門用語が患者を遠ざける現実
薬剤師は専門知識を持つがゆえに、専門用語を無意識に使ってしまいます。「副作用のモニタリング」「バイオアベイラビリティ」「薬物動態」といった言葉を、患者が理解できるはずがありません。
私が人事部長時代に受けた苦情の中で最も多かったのが「薬剤師の説明が難しすぎる」という内容でした。ある患者さんは「横文字ばかりで何も分からなかった。薬局を変えます」と言って去っていきました。
専門性をアピールしたい気持ちは分かります。しかしプレゼンテーションの目的は「知識の披露」ではなく「相手の理解と行動」です。
翻訳技術の具体的な方法
専門用語を患者に伝わる言葉に翻訳するコツは「身近な例え」と「数字の視覚化」です。
【翻訳の実例1:薬の作用機序】
- 専門用語:「この薬はACE阻害薬で、アンジオテンシン変換酵素を阻害して血圧を下げます」
- 翻訳後:「この薬は、血管を広げて血液の通り道を広くすることで、血圧を下げます。ホースを太くすると水の勢いが弱まるイメージです」
【翻訳の実例2:副作用のリスク】
- 専門用語:「この薬(ACE阻害薬)は副作用として空咳が出ることがあります」
- 翻訳後:「5人に1人くらいの割合で、風邪でもないのにコンコンと乾いた咳が出ることがあります。もし咳が続いて辛ければ、お薬を変えられるので教えてくださいね」
「時々出ます」と曖昧に言うより、「5人に1人(20%)」と伝えることで、患者さんは「自分にも起こりうることだ」と冷静に受け止め、副作用発現時もパニックにならずに相談してくれます。
医師への説明でも翻訳は必要
意外かもしれませんが、医師への説明でも翻訳技術は重要です。医師は薬の専門家ではありません。特に新薬や薬剤情報を伝える際、添付文書の丸写しでは伝わりません。
私の元部下だった薬剤師Cさんは、医師に新薬情報を提供する際、必ず「臨床現場での使い分け」に翻訳していました。「この薬は既存薬と比べて○○な患者さんに向いています」と具体的に説明する。その結果、医師からの信頼が厚く、処方提案も採用されやすくなりました。
ポイント3:「非言語コミュニケーション」で説得力を3倍にする
話す内容より話し方が印象を決める
心理学の研究では、コミュニケーションにおいて言葉そのもの(言語情報)だけでなく、声のトーンや話し方(聴覚情報)、表情や姿勢(視覚情報)といった非言語的な要素が、相手に与える印象を大きく左右することが知られています。つまり、何を話すかと同じくらい、どう話すかが重要になるのです。
私が採用面接で見ていたのも、まさにこの点でした。同じ志望動機を話しても、目を見て堂々と話す人と、下を向いてボソボソ話す人では、印象が全く違います。
薬剤師の業務でも同じです。服薬指導で原稿を読むように話す薬剤師と、患者の目を見て語りかける薬剤師。どちらが信頼されるかは明白です。
非言語コミュニケーションの具体的な改善点
医療現場で実践できる非言語コミュニケーションのポイントは以下の通りです。
【視線】 患者や医師の目を見て話す。ただし、ずっと見つめ続けるのではなく、3秒見て1秒外す程度のリズムが自然です。電子薬歴を見ながら話すのは避けましょう。
【声のトーン】 明るく、はっきりとした声で話す。特に高齢者への服薬指導では、普段より1トーン高めの声が聞き取りやすいです。早口は厳禁。ゆっくり、区切って話してください。
【姿勢と表情】 背筋を伸ばし、適度な笑顔を心がける。腕組みや無表情は威圧感を与えます。患者の話を聞く時は、相槌を打ちながら体を少し前に傾ける。これだけで「あなたの話を真剣に聞いています」というメッセージが伝わります。
疑義照会での非言語コミュニケーション
医師への疑義照会では、非言語コミュニケーションがさらに重要になります。忙しい医師に話しかける際、申し訳なさそうにモジモジしていては、相手にしてもらえません。
私が人事部長時代に高く評価していた薬剤師Dさんは、医師への疑義照会が非常に上手でした。彼女は医師に話しかける際、必ず背筋を伸ばし、明るく「先生、少しお時間よろしいですか」と声をかけていました。要件を伝える時も、資料を手に持ち、自信を持って話す。その姿勢が「この薬剤師は信頼できる」という印象を与えていたのです。
プレゼンテーション能力を磨く具体的な練習方法
録音・録画で自分の話し方を客観視する
自分の話し方のクセは、自分では気づきません。スマートフォンで服薬指導のロールプレイを録音・録画してみてください。
「えーっと」「あのー」といった口癖、早口、声の小ささ。客観的に見ると、改善点が明確になります。私が面接練習で応募者に録画を見せると、多くの人が「こんなに自信なさそうに話していたんですね」と驚きます。
同僚とのロールプレイ練習
一人で練習するより、同僚を相手にロールプレイをする方が効果的です。患者役、医師役を交代で演じ、フィードバックし合う。
特に有効なのが「3分間プレゼン」の練習です。新薬情報や症例報告を、3分間で分かりやすく説明する。時間制限があることで、結論ファーストと簡潔な説明が身につきます。
外部研修やセミナーの活用
プレゼンテーション能力は、専門のセミナーで学ぶのが最も効率的です。日本薬剤師会や各都道府県薬剤師会が開催する「コミュニケーション研修」「プレゼンテーションスキル向上セミナー」に参加してみてください。
また、転職を考えているなら、薬剤師専門の転職エージェントに相談するのも一つの方法です。面接対策としてプレゼンテーション技術の指導も行っています。転職活動を通じて、自分の話し方を客観的に見直す機会にもなるのです。
プレゼンテーション能力が年収とキャリアに与える影響
評価面談での自己PRが昇給を左右する
多くの薬局では年に1〜2回、評価面談が行われます。そこで自分の業務実績やスキルアップをアピールする必要があります。
しかしプレゼンテーション能力が低いと、どれだけ頑張っていても伝わりません。「特に何もしていません」と謙遜したり、「頑張りました」と抽象的に話したりする薬剤師が多いのです。
私が人事部長として評価面談に同席した際、ある薬剤師は「今期は在宅訪問を20件担当し、ポリファーマシー解消で5名の患者さんの薬剤数を平均3剤削減しました。結果として患者満足度が向上し、算定件数も前年比120%に増加しました」と具体的な数字で説明しました。
この薬剤師は昇給査定で最高評価を受け、年収が50万円アップしました。同じ業務をしていても、伝え方次第で評価は大きく変わるのです。
転職面接での合否を分けるプレゼンテーション力
転職面接では、限られた時間で自分の価値を伝える必要があります。ここでもプレゼンテーション能力が合否を分けます。
私が面接官として最も評価したのは「志望動機を3つのポイントで整理して話せる人」でした。逆に、思いつくままに話す人、質問に対して的外れな回答をする人は、どれだけ経験があっても採用しませんでした。
転職活動では、薬剤師専門エージェントを活用すると、面接でのプレゼンテーション指導を受けられます。模擬面接を通じて、自分の話し方の改善点を客観的に知ることができるのです。
管理職登用でも差がつく
薬局長や管理薬剤師を目指すなら、プレゼンテーション能力は必須です。部下への指導、経営層への報告、会議での発言。すべてがプレゼンテーションの場です。
私が見てきた優秀な管理職は、例外なく「伝える力」を持っていました。逆に、専門知識はあっても人を動かせない管理職は、チームの業績が上がりませんでした。
あなたの市場価値は伝え方で変わる
あなたは今、この記事を読んで何を感じているでしょうか。「自分は話し方が下手だから、ずっと損をしてきたのかもしれない」そう思っていませんか。
大丈夫です。プレゼンテーション能力は、後天的に磨ける技術です。専門知識は十分に持っているあなたなら、伝え方を少し変えるだけで、評価は劇的に変わります。
私が人事部長として多くの薬剤師を見てきた中で確信していることがあります。それは「あなたの市場価値は、あなたが思っているよりずっと高い」ということです。ただ、それを適切に伝えられていないだけなのです。
明日から、結論ファーストで話してみてください。専門用語を患者に分かる言葉に翻訳してみてください。患者の目を見て、明るく話しかけてみてください。
小さな変化の積み重ねが、あなたのキャリアを変えます。今の職場で評価されたいなら、プレゼンテーション能力を磨くことです。もし今の職場では評価されないと感じているなら、あなたの能力を正当に評価してくれる職場を探すべきです。
転職を考えているなら、薬剤師転職エージェントに相談してみるのが最適解です。
実は、人事部長として多くの紹介会社と付き合う中で、「この会社の担当者からの電話なら、どんなに忙しくても取る」と決めていた会社が数社だけありました。なぜ彼らは特別だったのか?どうすれば、あなたの年収を最大化してくれる「本物の担当者」に出会えるのか。
ここで書くと長くなるため、採用担当しか知らない「エージェント活用の裏ノウハウ」として別の記事にまとめました。本気で転職を成功させたい方だけご覧ください。