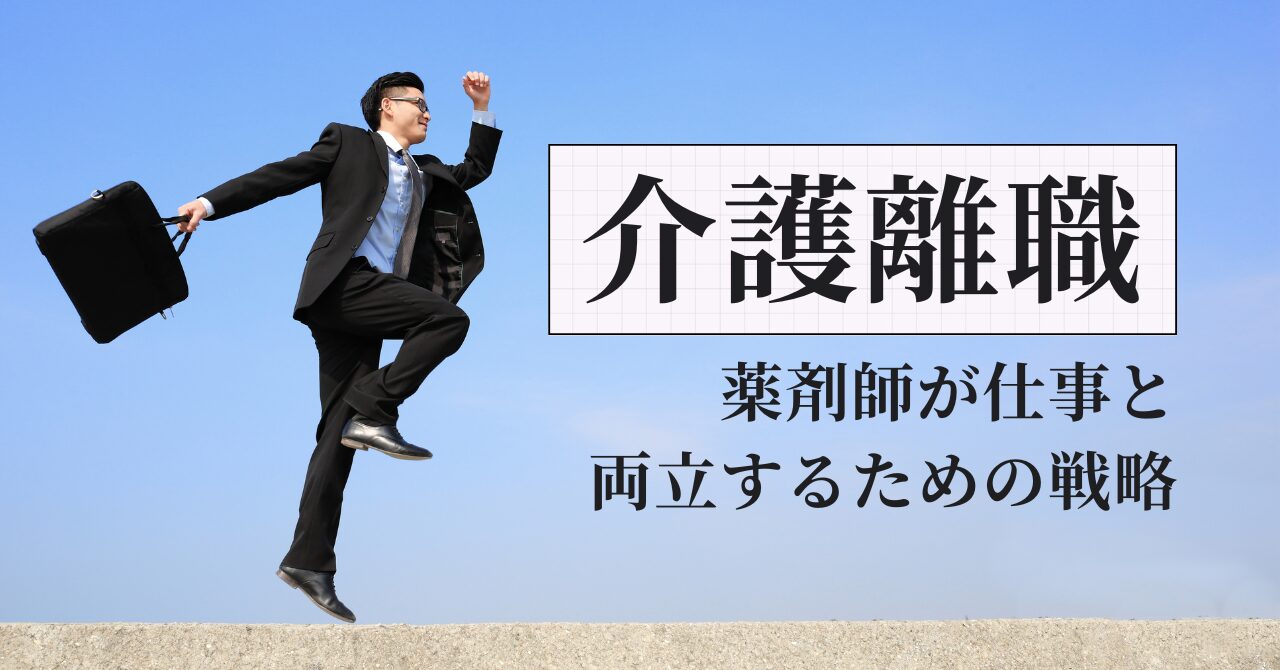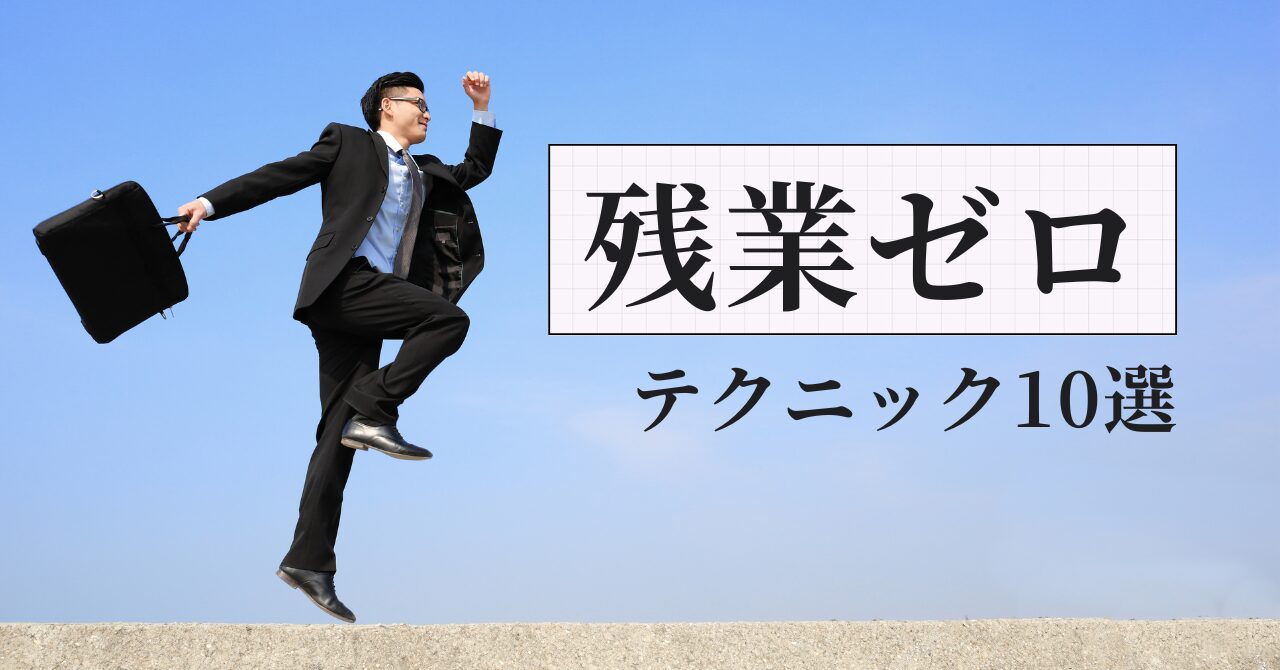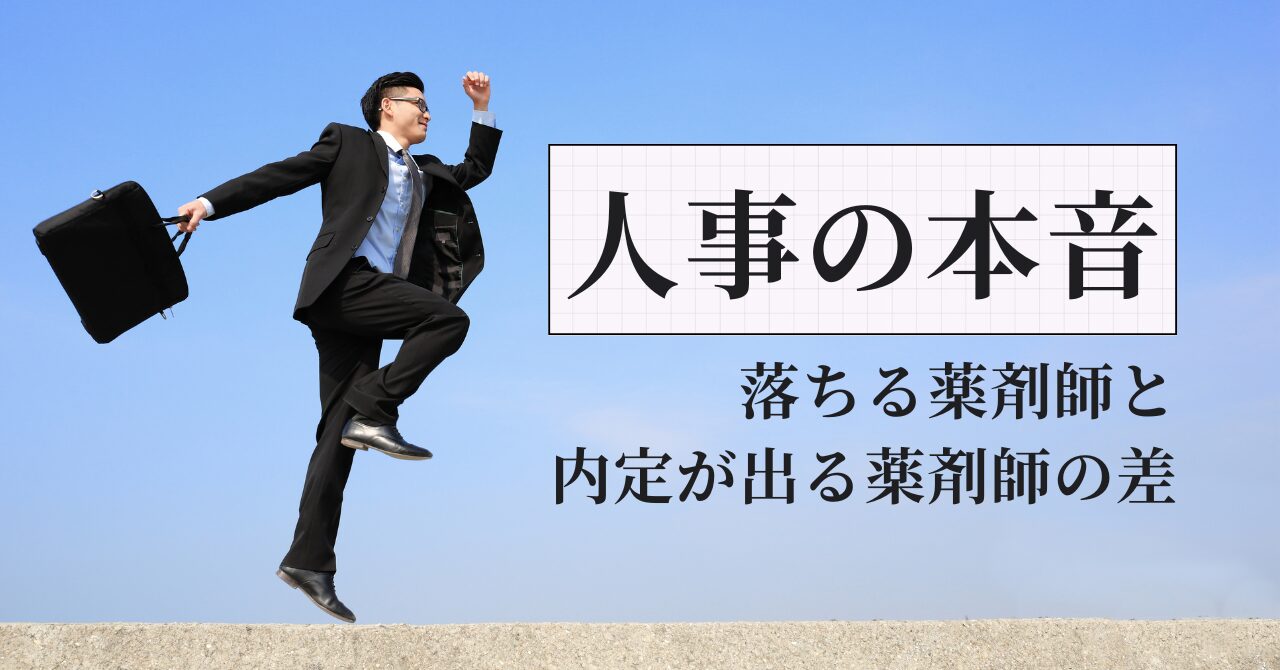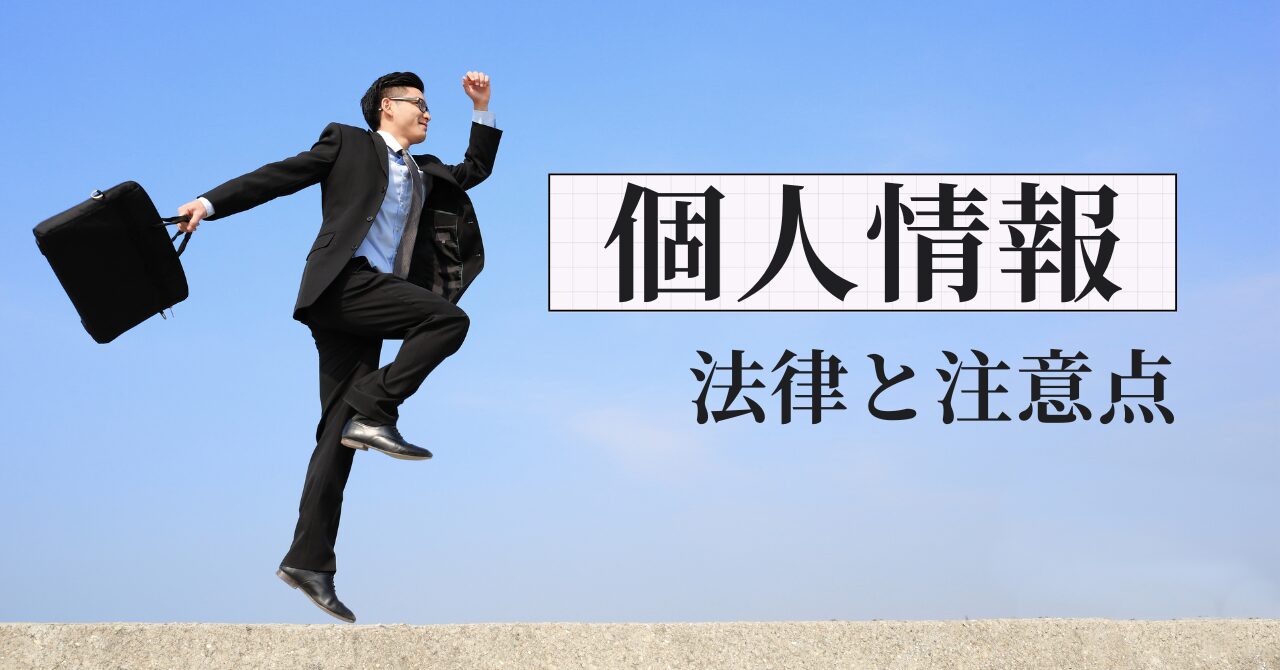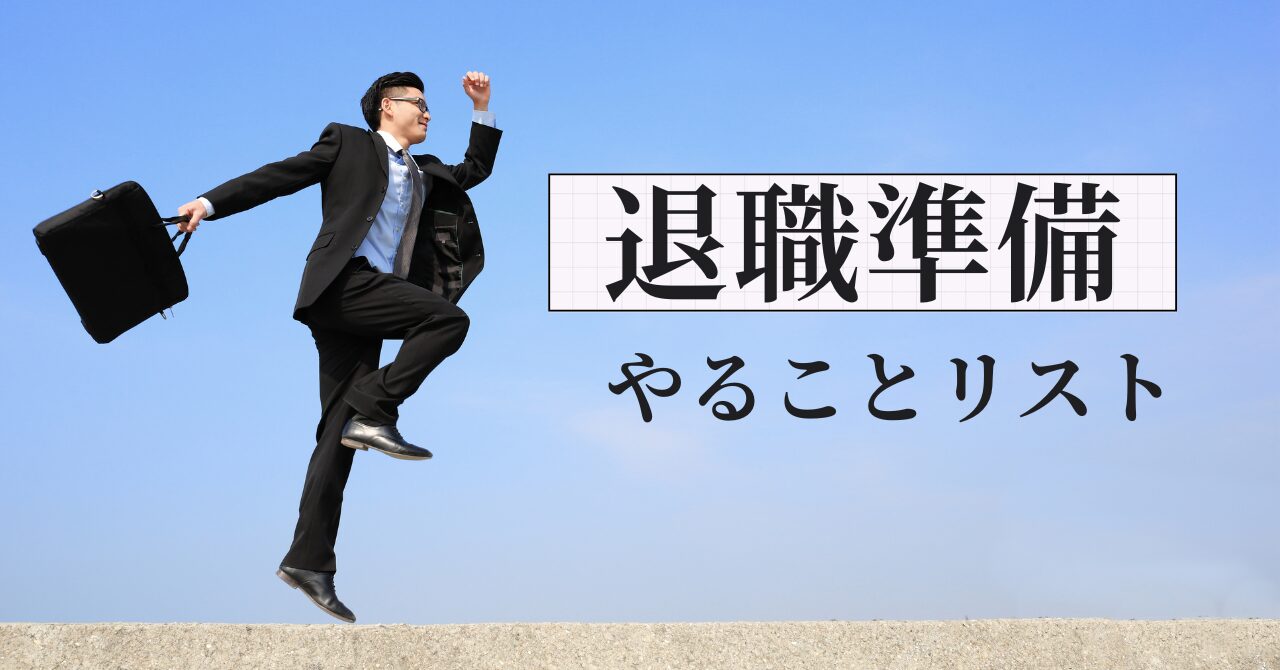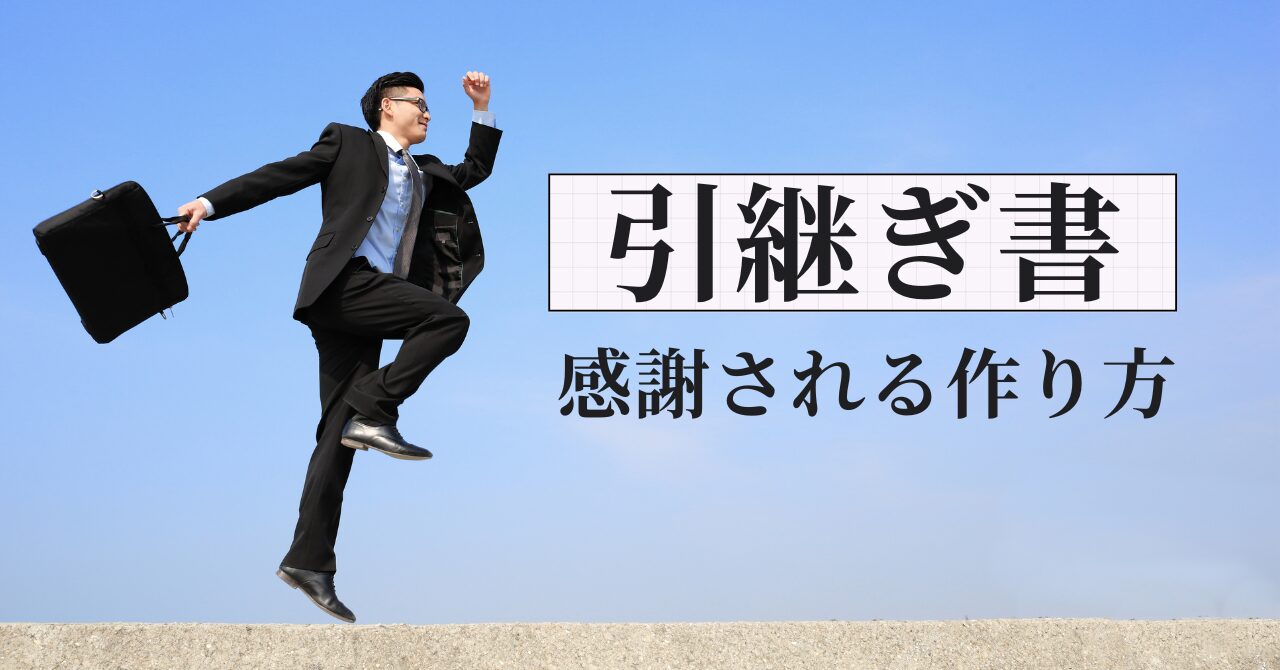※2025年9月時点の情報です
「介護離職」という言葉が頭をよぎった瞬間、あなたの生涯賃金は数千万円単位で消失するリスクに晒されています。
元人事部長として断言します。「親のために仕事を辞める」は、親にとってもあなたにとっても、最悪の選択です。
親の医療費を誰が払うのですか? あなたの老後は誰が守るのですか?
感情論で辞表を書く前に、この「戦略」を読んでください。
介護離職という選択肢を選ぶ前に知っておくべきこと
「親の介護が必要になった。仕事を辞めるしかないのか」
そう考えているあなたに、まず伝えたいことがあります。
介護離職は、あなたの人生に想像以上の経済的ダメージを与えます。厚生労働省の調査によれば、介護を理由に離職した人の約7割が経済的な困難を経験しています。年収が途絶えるだけでなく、再就職時の年収は離職前の6割程度に下がるケースが大半です。
| 項目 | A:感情で「介護離職」 | B:制度利用で「継続」 |
|---|---|---|
| 直後の収入 | 0円(無収入) | 給与の67%(給付金) ※社会保険料免除あり |
| 再就職/復帰 | パート・派遣が中心 年収大幅ダウン |
正社員として復帰 (短時間勤務など) |
| 5年間の損失 | 約1,500万円以上の損失 ※年収500万→200万の場合 |
現状維持~微減 ※キャリア継続 |
| 老後の厚生年金 | 大幅に減額 | 納付継続のため満額 |
実は日本には、仕事と介護を両立するための制度が数多く存在します。介護休業制度、短時間勤務、在宅勤務、そして地域の公的サポート。これらを戦略的に組み合わせることで、年収を大きく下げずに親の介護を続けることは十分に可能です。
本記事では、元人事部長の視点から、介護離職を防ぐための具体的な戦略をお伝えします。制度の使い方、職場への交渉術、そして多くの人が見落としている公的サポートまで、実務レベルで解説していきます。
あなたのキャリアも、親の介護も、両方を守る方法は必ずあります。
ポイント1:介護休業制度を「緊急対応」として正しく使え
介護休業制度について、多くの人が誤解しています。
「介護休業=介護のために長期間休む制度」と考えていませんか。実は違います。介護休業制度の本来の目的は、介護体制を整えるための準備期間を確保することです。
育児介護休業法で定められた介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できます。この93日間を使って何をすべきか。答えは「持続可能な介護体制の構築」です。
具体的には以下の準備を進めます。ケアマネージャーとの面談設定、介護サービス事業者の選定、地域包括支援センターへの相談、必要な介護認定の申請、家族間での役割分担の協議。これらを計画的に実行するための時間が介護休業です。
| 期間 | フェーズ | 元人事部長推奨 具体的なTODO |
|---|---|---|
| 1~2週目 | 現状把握・申請 | ・地域包括支援センターへ連絡 ・要介護認定の申請(役所) ・親の資産/医療保険の確認 |
| 3~8週目 | 体制構築 | ・ケアマネジャー選定とプラン作成 ・施設見学・サービス契約 ・家族会議(金銭・役割分担) |
| 9~12週目 | リハーサル | ・サービス利用開始(慣らし) ・職場との復帰面談(働き方交渉) ・自分不在でも回るかテスト |
私が対応したケースで印象的だったのは、薬剤師のCさんです。母親が急に倒れ「辞めます」と申し出てきました。しかし制度を説明し、まず2週間の介護休業を取得してもらいました。
その間にCさんは要介護認定を申請し、ケアマネージャーと介護プランを作成。デイサービスと訪問介護を組み合わせることで、平日日中の介護負担を大幅に軽減できました。結果として、Cさんは仕事を続けながら母親を支えています。
介護休業制度を使う際の注意点があります。休業開始予定日の2週間前までに、書面で会社に申し出る必要があります。また、休業中は雇用保険から介護休業給付金が支給され、休業開始時賃金の67%が支給されます。
これは無給ではありません。経済的な不安を最小限に抑えながら、介護体制を整える時間を確保できるのです。
ポイント2:短時間勤務と時差出勤で日常介護に対応する
介護体制を整えた後も、通院の付き添いや急な呼び出しへの対応が必要になります。
ここで活用すべきが、介護のための短時間勤務制度と時差出勤です。育児介護休業法では、事業主に対して介護のための所定労働時間の短縮措置などを講じることを義務付けています。
具体的な選択肢は企業によって異なりますが、一般的には以下のような措置が用意されています。短時間勤務制度(1日の所定労働時間を短縮)、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ繰下げ、介護サービス費用の助成。
薬局勤務の場合、シフト制が多いため柔軟な対応が難しいと思われがちです。しかし実際には、交渉次第で調整可能なケースは多くあります。
ここで重要なのは、職場への伝え方です。単に「早退させてほしい」と頼むのではなく、「朝のシフトで対応できないか」と代替案を提示することです。人事の立場から言えば、業務への影響を最小限にする提案をされると、承認しやすくなります。
また、在宅勤務の活用も検討すべきです。薬剤師の場合、調剤業務は在宅では不可能ですが、薬歴記入や医薬品情報の整理などの事務作業は自宅でも可能です。週1回でも在宅勤務の日があれば、介護の時間を確保しやすくなります。
短時間勤務を選択した場合、当然ながら給与は減少します。しかし、完全に離職するよりも経済的ダメージははるかに小さいのです。
ポイント3:介護休暇を計画的に使い切る戦略を立てる
介護休業とは別に、介護休暇という制度があります。
介護休暇は年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)を、1日単位または時間単位で取得できる制度です。通院の付き添い、ケアマネージャーとの面談、役所での手続きなど、突発的な対応に使えます。
多くの人がこの制度の存在を知りません。有給休暇とは別に、介護のために使える休暇が法律で保障されているのです。
私が人事部長として採用面接を行っていた際、転職理由として「前の職場では介護休暇を取らせてもらえなかった」という話を何度も聞きました。しかし、これは明確な法律違反です。企業は介護休暇の取得を拒否できません(※時間単位の取得については、労使協定により一部対象外となる場合があるため、就業規則の確認が必要です)。
介護休暇の戦略的な使い方を説明します。
まず、年度初めに介護に必要な日数を概算します。定期通院が月1回なら年12回、ケアマネージャーとの面談が3ヶ月に1回なら年4回。このように必要日数を見積もり、介護休暇と有給休暇をどう配分するか計画を立てます。
薬剤師のEさんは、母親の定期通院に毎月半日が必要でした。時間単位の介護休暇を使い、午後3時間だけ休むことで、年間36時間(4.5日分)を通院に充てました。残りの0.5日分は、急な呼び出しに備えて確保しておいたのです。
介護休暇は無給の企業が多いですが、有給休暇を温存できるメリットは大きいです。有給休暇は自分のリフレッシュのために使い、介護対応には介護休暇を使う。この使い分けが、長期的な介護生活を乗り切るコツです。
また、時間単位で取得できることも重要なポイントです。「半日休むほどではないが2時間だけ抜けたい」という状況は頻繁に発生します。時間単位の介護休暇なら、こうした細かいニーズに柔軟に対応できます。
介護保険サービスと地域包括支援センターをフル活用する
仕事と介護の両立において、最も重要なのは「一人で抱え込まない」ことです。
日本の介護保険制度は、要介護認定を受けることで様々なサービスを利用できます。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具のレンタルなど、選択肢は多岐にわたります。
要介護認定の申請は、市区町村の窓口や地域包括支援センター、またはケアマネージャーに代行してもらうことも可能です。申請から認定まで約1ヶ月かかるため、早めの手続きが重要です。
認定を受けると、ケアマネージャーがケアプランを作成します。このケアマネージャーとの関係が、両立生活の質を大きく左右します。
私の元部下のFさんは、最初に紹介されたケアマネージャーとの相性が合わず、サービス内容に不満がありました。しかし、ケアマネージャーは変更できることを知り、別の事業所に依頼しました。新しいケアマネージャーは、Fさんの仕事の状況を理解し、デイサービスの曜日を調整してくれました。
地域包括支援センターは、介護に関する総合相談窓口です。介護保険サービスだけでなく、生活支援サービス、権利擁護、虐待防止など、幅広い支援を行っています。
具体的には、こんな相談ができます。「親が認知症かもしれない。どこに相談すればいいか」「介護サービスの使い方が分からない」「仕事をしながら介護する方法を知りたい」。専門職が無料で相談に応じてくれます。
介護保険サービスの自己負担は、原則として1割(所得に応じて2割または3割)です。例えば、月に20万円分のサービスを利用しても、自己負担は2万円です。仕事を続けることで得られる収入と比較すれば、サービスを利用する経済的メリットは明らかです。
職場への伝え方と交渉術|人事が本音で語る
介護の状況を職場にどう伝えるか。これは非常に重要な問題です。
結論から言えば、早めに、具体的に、そして前向きに伝えることが最善の方法です。「親の介護が必要になりました。制度を利用しながら仕事を続けたいと考えています」という姿勢で臨むことです。
人事の立場から言えば、突然「辞めます」と言われるよりも、「こういう状況なので、こう働きたい」と相談される方が、はるかに対応しやすいのです。
職場への伝え方で避けるべきは、曖昧な表現です。「ちょっと家庭の事情で」「少し休みが必要で」といった言い方では、職場側も適切な支援策を考えられません。
具体的に伝えるべき情報は以下の通りです。要介護者の状態(要介護度、主な症状)、必要な対応の頻度(週1回の通院、月2回のケアマネ面談など)、希望する働き方(短時間勤務、時差出勤、在宅勤務など)、利用したい制度(介護休業、介護休暇など)。
私が人事部長時代、薬剤師のGさんから介護の相談を受けました。Gさんは最初、遠慮がちに「少し早退が増えるかもしれません」とだけ伝えてきました。
しかし詳しく聞くと、父親が要介護3の認定を受け、週2回のデイサービス利用を検討中でした。そこで私から「デイサービスの送り出しに30分必要なら、始業時間を30分遅らせる方法もある」と提案しました。Gさんは「そんなことができるとは思わなかった」と驚いていました。
職場との交渉では、具体的な代替案を示すことが重要です。「週1回在宅勤務にしてほしい」だけでなく、「水曜日は薬歴入力日として在宅勤務にし、その分月曜日の出勤を1時間早める」といった提案です。
人事担当者は、業務への影響を最小限にしながら、従業員を支援したいと考えています。Win-Winの提案をすることで、交渉は格段にスムーズになります。
転職という選択肢|介護に理解ある職場を見極める方法
どうしても今の職場で両立が難しい場合、転職も選択肢の一つです。
ただし、介護を理由に焦って転職すると、かえって状況が悪化するケースがあります。転職先の選び方には、明確な基準が必要です。
介護に理解のある職場を見極めるポイントを説明します。
まず、求人票で確認すべきは、介護関連制度の記載です。「介護休業取得実績あり」「短時間勤務制度」「在宅勤務可」といった記載がある企業は、制度を実際に運用している可能性が高いです。
逆に注意すべきは「アットホームな職場」「家族的な雰囲気」といった曖昧な表現だけの求人です。こうした企業では、制度はあっても「みんな頑張っているのに」という雰囲気で利用しづらいケースがあります。
面接では、介護の状況を正直に伝えることをお勧めします。「現在、親の介護をしながら働いています。御社の介護支援制度について教えていただけますか」と質問するのです。
この質問への回答で、企業の本気度が分かります。具体的な制度や取得実績を説明できる企業は信頼できます。逆に、曖昧な回答や「前向きに検討します」といった返答の企業は、実際の運用が伴っていない可能性があります。
転職エージェントを活用する場合、介護の状況を最初に伝えることが重要です。優秀なエージェントなら、介護と両立しやすい職場を優先的に紹介してくれます。
転職で重要なのは、年収だけを見ないことです。介護との両立を優先するなら、柔軟な働き方ができる職場を選ぶべきです。年収が多少下がっても、長期的に働き続けられる環境の方が、トータルの収入は大きくなります。
私が人事部長時代、実際に『交渉力が高く、信頼できる』と感じたエージェントについては、以下の記事で実名を挙げて解説しています。失敗したくない方は、必ずチェックしてください。

経済的支援制度を見落とすな|介護にかかる費用を減らす方法
介護には、想像以上にお金がかかります。
しかし、多くの人が利用できる経済的支援制度を知りません。知らないために、本来払わなくてもいい費用を負担しているケースが多いのです。
まず、高額介護サービス費制度です。月の介護サービス自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の場合、上限は44,400円です。
この制度は自動的に適用されるわけではありません。市区町村の窓口で申請が必要です。多くの人がこの手続きを忘れ、払い戻しを受けていません。
次に、医療費控除です。介護サービスの一部は医療費控除の対象になります。訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなどが該当します。確定申告で控除を受けることで、税金が還付されます。
障害者控除は「手帳」がなくても受けられる可能性があります。重要なのは、要介護認定を受けただけでは自動適用されないという点です。 市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」を別途申請し、発行してもらう必要があります。この紙一枚あるだけで、数十万円の所得控除(節税)になるケースがあるのです。人事部長時代、これを知らずに損をしている薬剤師を何人も見てきました。
私の元部下のHさんは、母親が要介護4でした。私がこれらの制度を説明すると、Hさんは「そんな制度があるなんて知らなかった」と驚きました。手続きをした結果、年間で約15万円の負担軽減につながったのです。
さらに、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度もあります。介護のために一時的に費用が必要な場合、低利または無利子で借りられる制度です。全ての人が対象ではありませんが、条件に該当すれば選択肢の一つになります。
介護タクシーの助成制度も自治体によっては存在します。通院時のタクシー代を補助してくれる制度で、年間数万円の節約になります。
こうした制度の情報は、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談すれば教えてもらえます。しかし、自分から聞かないと教えてもらえないケースも多いのです。積極的に情報収集することが、経済的な負担を減らす第一歩です。
| 制度名 | メリット・金額目安 | 申請先 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 月額上限(約4.4万円)を超えた分が戻る | 市区町村 |
| 障害者控除 | 要介護認定でも対象の可能性大。 所得税・住民税が数万~十数万円安くなる |
市区町村 →税務署 |
| 家族介護慰労金 | 介護サービスを使わず介護している場合に支給(年10万円程度※自治体による) | 市区町村 |
| 介護休業給付金 | 休業中、賃金の67%を支給。 ※非課税のため手取りは8割近い感覚 |
ハローワーク (会社経由) |
多くの薬剤師さんが「私の個人的な事情で会社に条件をのんでもらうなんて」と萎縮してしまいます。
しかし、人事部長として社内運営をしていた私からすれば、真実は逆です。
薬剤師であるあなたが辞めた場合、新しい人を採用するためのコストが発生します。加えて、その人が現場に慣れるまでの教育コストも発生します。
また店舗サイドから見ても、社員がコロコロ入れ替わる環境では就業のモチベーションは生まれにくいです。
つまり、あなたが「時短勤務でもいいから残ってくれる」ことは、会社にとってもメリットがあるのです。あなたの交渉は「わがまま」ではありません。
会社にとっても利益のある「対等なビジネス提案」なのです。自信を持って切り出してください。
あなたのキャリアを守りながら親を支える未来は実現できる
今の環境で悩み続けたあなたを、誰も責めることはできません。
親の介護と仕事の両立は、誰にとっても簡単なことではありません。しかし、だからこそ伝えたいのです。あなた一人で抱え込む必要はないということを。
日本には、仕事と介護を両立するための制度が確実に存在します。介護休業、短時間勤務、介護休暇、そして地域の公的サポート。これらを戦略的に組み合わせることで、キャリアを守りながら親を支えることは可能です。
私が人事部長として見てきた多くの薬剤師たちは、制度を知ることで人生の選択肢が広がりました。「辞めるしかない」と思い詰めていた人が、働き方を調整することで両立を実現しています。
ただし、「理解のある職場」は、求人サイトの検索条件には出てきません。
なぜなら、本当に働きやすい薬局は離職率が低く、表立った求人を出す必要がないからです。そうした「プラチナ求人」は、信頼できるエージェントが水面下で持っている「非公開求人」の中にしかありません。
親が倒れてからでは、冷静な判断はできません。「まだ大丈夫」な今だからこそ、情報収集を始めてください。
2月は求人数が最大化しますが、同時に「4月入職」を目指すライバルも激増します。人事の経験上、この時期に焦って転職先を決め、入社後に「聞いていた話と違う」と後悔する薬剤師の方を数多く聞きます。
今の時期に必要なのは、大量の求人票ではありません。その中から「地雷」を取り除き、あなたに最適な「正解」だけを提示してくれる信頼できるエージェントの存在です。
納得のいく環境で最高のスタートを4月に迎えるために。私が人事責任者として20社以上と折衝し、「ここなら家族にも勧められる」と認定したエージェントだけを厳選しました。4月からの新生活を確実に手に入れたい方は、今すぐ確認してください。
あなたの薬剤師としてのキャリアが、より良い方向に進むことを心から願っています。
あなたのキャリアは、あなたが積み重ねてきた努力と経験の結晶です。親の介護も大切ですが、あなた自身の人生も同じくらい大切です。両方を守る方法は必ずあります。
制度を知り、サポートを活用し、戦略的に動くこと。それが、介護離職を防ぎ、あなたの人生を守る唯一の方法です。
今日から、小さな一歩を踏み出してください。地域包括支援センターに電話をする、職場に相談する、転職エージェントに登録する。どれでも構いません。
あなたの未来は、今日のあなたの行動で変わります。
- 職場に迷惑をかけるのが申し訳なくて、交渉できません。
-
人事の視点では、あなたが突然辞める方が迷惑であり、コストもかかります。薬剤師を1名採用するには100万円以上のコストと時間がかかります。あなたが制度を使って働き続けてくれることは、会社にとっても「採用コスト減」「戦力維持」という大きなメリットがあるのです。堂々と交渉してください。
- 介護休業給付金の67%だけで生活できるか不安です。
-
額面は67%ですが、休業中は「社会保険料(健康保険・厚生年金)」が免除されます。また、給付金は非課税なので所得税も引かれません。そのため、実際の手取り額としては働いている時の「約8割」程度が確保されます。一時的な期間であれば、十分に生活可能な水準です。
- パート薬剤師でも介護休業は取得できますか?
-
はい、一定の条件を満たせば取得可能です。「入社して1年以上経過している」「申し出時点で、取得予定日から93日経過後も雇用継続が見込まれる」などの条件があります。社内の人事労務部門へご相談することをお勧めします。諦めずに確認してください。