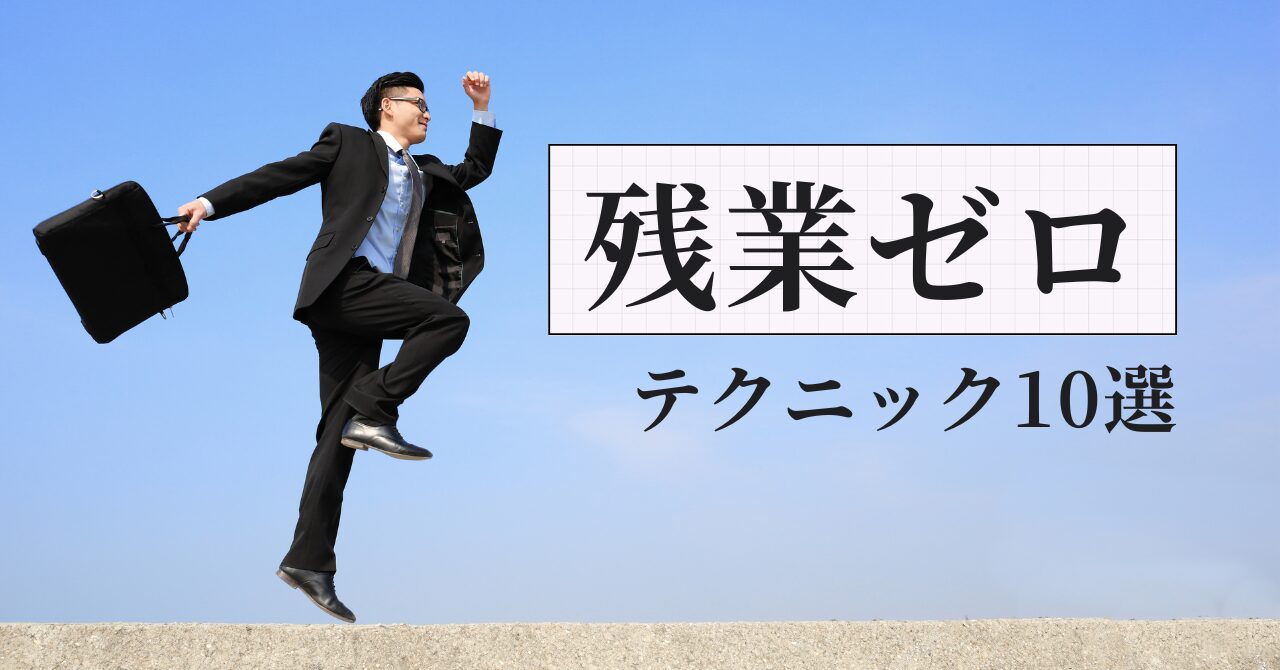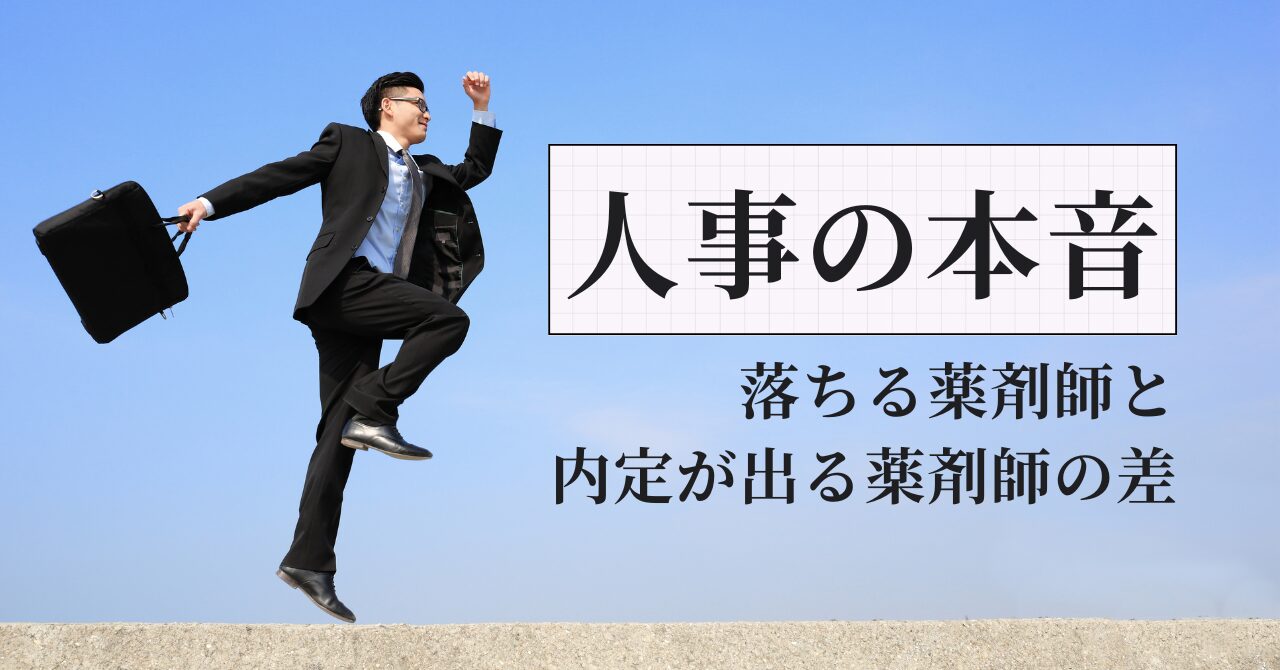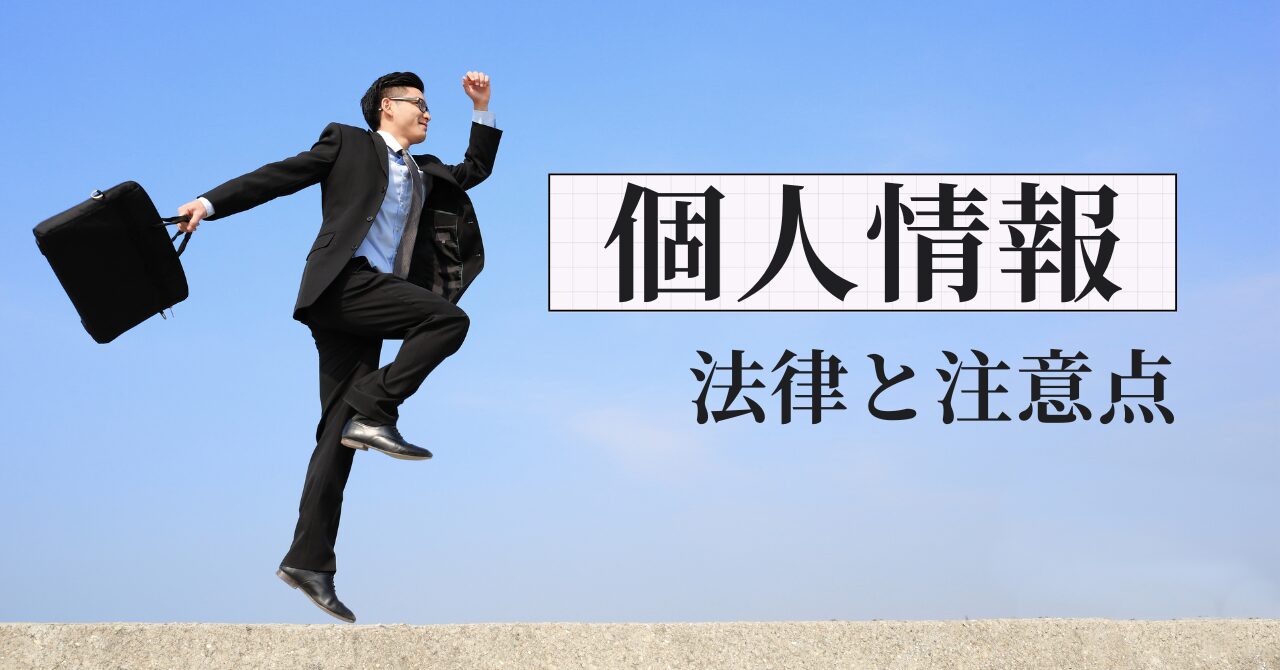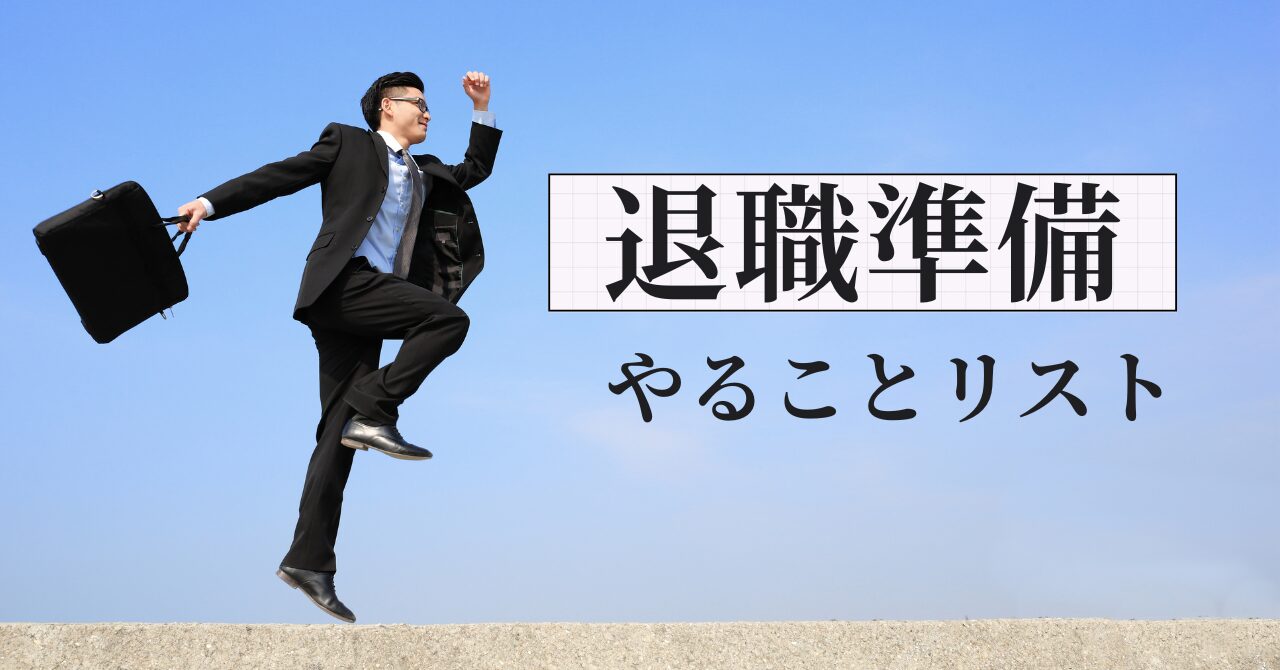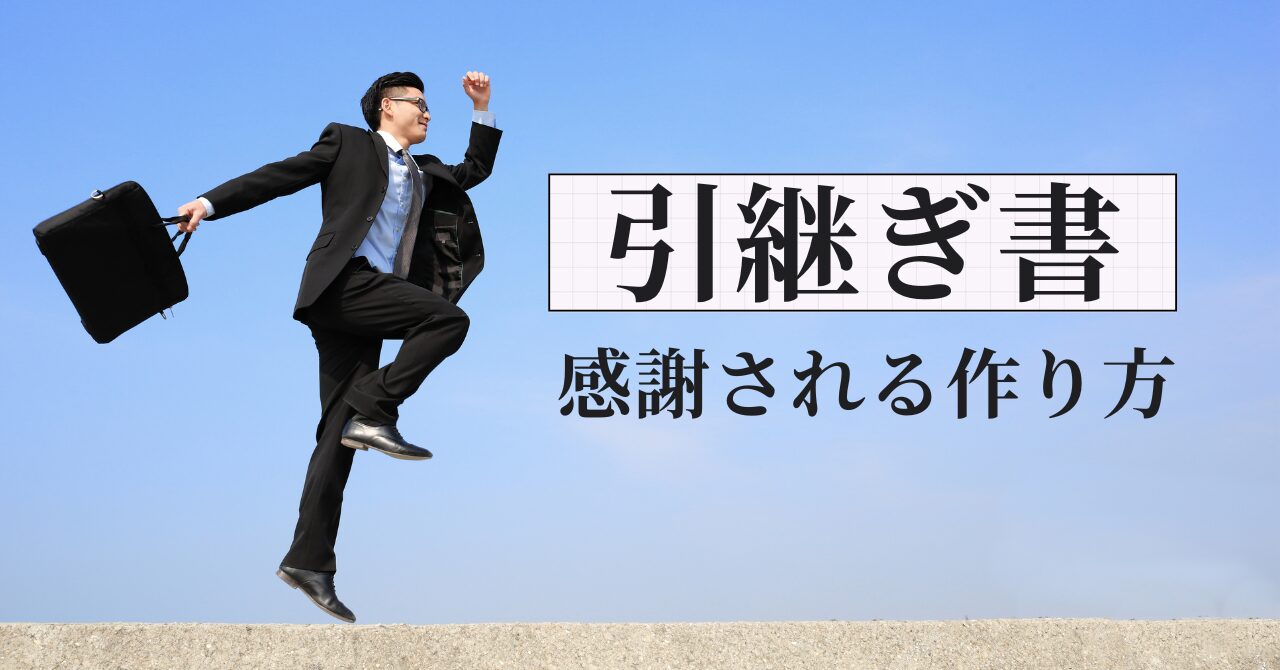2025年10月時点の情報です。
あなたの残業時間、本当に必要なものですか?
毎日の残業が当たり前になっていませんか?
閉局時間を過ぎても終わらない薬歴入力。 休憩時間を削って対応する在庫管理。 帰宅後も頭から離れない、明日の業務への不安。
厚生労働省の統計では薬剤師の平均残業時間は月11時間程度とされていますが、現場の実感値は異なります。「サービス残業」や「持ち帰り業務」を含めれば、月20時間を超えて疲弊している薬剤師は少なくありません。
しかし、この業界に長くいる者として多くの薬局を見てきた経験から断言できます。 その残業の大半は、業務の進め方を変えるだけで削減できるものです。
「人手不足だから仕方ない」 「患者さんのためだから我慢するしかない」
そう諦めていた薬剤師たちが、業務効率化によって残業ゼロを実現した事例を、私は数多く見てきました。
本記事では、調剤薬局チェーンの人事部長・経営コンサルタントとして現場改善に携わってきた経験から、薬剤師が今日から実践できる業務効率化テクニックを10個厳選してお伝えします。
残業ゼロは夢ではありません。 正しい方法を知り、実践すれば必ず実現できます。

残業が発生する本当の理由
業務効率化の前に知るべき「残業の構造」
残業削減を語る前に、まず残業が発生する本質的な理由を理解する必要があります。
| 項目 | 残業が多い薬局(非効率型) | 残業ゼロの薬局(効率特化型) |
| 業務の優先順位 | 到着した処方箋から順に処理 | 受付時に「急ぎ・通常」を仕分け |
| 薬歴入力のタイミング | 閉局後にまとめて一括入力 | 投薬直後の5分で「リアルタイム入力」 |
| 在庫・発注管理 | 経験則による目視と手動発注 | システム連携による自動発注 |
| スタッフの役割 | 全員が全業務をこなす(属人化) | 0402通知に基づく適切なタスクシフト |
| 情報共有の手段 | 紙のメモや口頭伝達(ミス多) | チャットツール等によるデジタル共有 |
私が人事部長や経営コンサルタントとして様々な店舗を視察した際、残業が慢性化している薬局には共通点がありました。
それは「忙しいから残業する」のではなく「非効率な業務フローが残業を生んでいる」という事実です。
処方箋枚数が1日80枚の薬局で残業ゼロを実現している店舗がある一方、60枚でも毎日2時間残業している店舗もありました。
この差は何か?
業務の進め方です。
多くの薬剤師は、新人時代に教わった業務手順をそのまま続けています。 しかし、その手順は本当に最適でしょうか?
調剤報酬改定や電子薬歴の進化により、薬剤師業務は大きく変化しています。 にもかかわらず、10年前と同じやり方を続けている薬局が非常に多いのです。
残業ゼロを実現するには、まず「今の業務フローは最適か?」と問い直すことから始める必要があります。
ポイント1:処方箋受付の時点で業務量を8割決める
受付時の情報収集が全てを変える
残業削減の第一歩は、処方箋受付の段階にあります。
ここでの対応が、その後の業務負荷を大きく左右するからです。
私が管理していた薬局で、残業ゼロを実現したCさんの事例を紹介します。
Cさんは受付時に必ずこう患者さんに確認していました。
「今日は急いでいらっしゃいますか?お時間に余裕はありますか?」
この一言で、調剤の優先順位を瞬時に判断できるようになります。
さらに重要なのは、お薬手帳の確認です。 多くの薬剤師は調剤後に確認しますが、Cさんは受付時点で併用薬をチェックしていました。
この習慣により、疑義照会が必要なケースを事前に把握できます。 調剤中に「あ、これ疑義照会が必要だ」と気づいて作業が止まることがなくなるのです。
受付時に確認すべき5つのポイント
- 患者さんの待ち時間の余裕度
- お薬手帳での併用薬チェック
- 前回と処方内容の変更点
- ジェネリック医薬品への変更希望
- 服薬状況や残薬の有無
受付担当が事務員の場合でも、これらの情報をメモで共有する仕組みを作ることで、調剤の流れが劇的にスムーズになります。
受付は単なる「処方箋を受け取る作業」ではありません。 その後の業務全体を設計する重要なプロセスなのです。
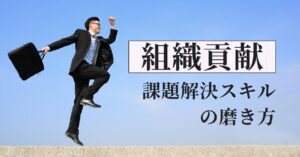
ポイント2:調剤の優先順位を「見える化」する
混乱を防ぐ視覚的管理の威力
複数の処方箋が同時進行する調剤室では、優先順位の管理が残業削減の鍵を握ります。
私が視察したある薬局では、調剤棚に色分けされた付箋を貼るシンプルな方法で残業を30%削減しました。
赤い付箋は「急ぎ」、黄色は「通常」、青は「時間に余裕あり」という具合です。
この視覚化により、薬剤師全員が瞬時に優先順位を把握できるようになります。
「次はどれを調剤すればいい?」という確認作業がなくなるだけで、1日あたり15分の時短になるという試算もあります。
さらに効果的なのは、調剤の進捗状況も見える化することです。
付箋の位置を「未着手」「調剤中」「監査待ち」「投薬準備完了」と移動させることで、チーム全体の状況が一目で分かります。
一人薬剤師の場合でも、この方法は有効です。 自分の作業状況を視覚的に把握することで、「あれもこれも」という焦りが軽減されます。
業務の見える化は、特別なシステム導入を必要としません。 付箋とホワイトボードがあれば、今日から実践できるのです。
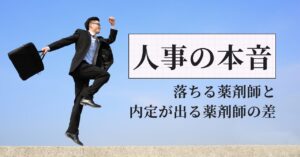
ポイント3:薬歴入力を「リアルタイム化」する
閉局後の薬歴地獄から解放される方法
薬剤師の残業理由で最も多いのが、閉局後の薬歴入力です。
「投薬が終わってから書こう」と後回しにした結果、閉局後に1時間以上かかるケースは珍しくありません。
しかし、残業ゼロを実現している薬剤師は、投薬直後に薬歴を入力しています。
私の元部下だったDさんは、この習慣で残業時間を月40時間削減しました。
Dさんが実践していたのは 投薬終了後、速やかに薬歴の骨子を入力してしまうというものです。
完璧な薬歴を書こうとすると時間がかかります。 しかし、骨子さえ残しておけば、後から詳細を追記するのは簡単です。
電子薬歴の多くには、音声入力機能やテンプレート機能が搭載されています。 これらを活用すれば、薬歴入力時間は大幅に短縮できます。
薬歴を素早く書くための実践テクニック
- 頻出する指導内容をテンプレート化する
- 音声入力機能を積極的に使う
- 患者さんとの会話中にキーワードをメモする
- SOAP形式にこだわりすぎない
- 完璧を目指さず、必要最小限の記録から始める
| ステップ | 従来のやり方(NG例) | 効率化のやり方(推奨例) | 削減効果(目安) |
| 1. メモ取り | 投薬後に記憶を頼りに書く | 指導中にキーワードをPOS入力 | 10分/日 |
| 2. 下書き | 閉局後に白紙から書き始める | 投薬終了直後に「骨子」のみ作成 | 20分/日 |
| 3. テンプレ活用 | 毎回全ての文章を手入力 | 疾患別の定型文を辞書登録 | 15分/日 |
| 4. 記録の精査 | 完璧な「読み物」を目指す | 法律上の必須項目に集中する | 15分/日 |
| 合計削減時間 | – | 毎日 約60分の短縮 | 月20時間削減 |
薬歴は「読み物」として完璧に仕上げる必要はありません。薬剤師法等の記載要件を満たす必要最小限の事実記録があれば、監査上も法的にも問題ありません。
閉局後の薬歴入力は、もはや時代遅れの習慣です。 リアルタイム記録に切り替えることで、あなたの残業時間は確実に減ります。
ポイント4:在庫管理を「自動化」する
発注業務に時間を奪われるのは今日で終わり
在庫管理と発注業務は、多くの薬剤師が「仕方ない残業」と考えている領域です。
しかし、この業務こそ自動化の余地が最も大きいのです。
AIを搭載した在庫管理システムを導入することで、発注作業時間が週5時間から30分に短縮された事例もあるようです。
また最新の電子薬歴システムには、処方箋データと連動した自動発注機能が搭載されています。
設定した在庫基準を下回ると、自動的に発注リストが作成される仕組みです。
「うちの薬局にそんなシステムはない」という方も諦める必要はありません。
エクセルで簡易的な在庫管理表を作成するだけでも、効率は大きく改善されます。
ある知り合いの薬局では、医薬品ごとに「最小在庫数」「発注単位」「発注先」を一覧化したエクセルシートを作成しました。
この表を見ながら発注するだけで、在庫確認の時間が半減したのです。
さらに効果的なのは、発注タイミングの最適化です。
多くの薬局では「在庫が少なくなったら発注」という曖昧な基準で動いています。 これでは欠品リスクもあれば、過剰在庫も発生します。
処方頻度データを分析し、薬剤ごとに最適な発注タイミングを設定することで、在庫管理の精度が飛躍的に向上します。
在庫管理業務は、あなたの専門性を発揮する場ではありません。システムに任せられる部分は任せ、患者さんとの対話に時間を使うべきです。
ポイント5:疑義照会を「標準化」する
医療機関との連携をスムーズにする仕組み作り
疑義照会は避けられない業務ですが、その進め方次第で時間効率は大きく変わります。私が視察した薬局の中で、疑義照会に最も時間がかかっていたのは、連絡先や確認項目が整理されていない店舗でした。
「あの先生の連絡先どこだっけ?」 「前回はどう対応したっけ?」
こうした確認作業が、疑義照会を長引かせているのです。
残業ゼロを実現した薬局では、医療機関ごとに「疑義照会シート」を作成していました。このシートには、診療所の連絡先、対応時間、よくある疑義内容とその回答パターンが記録されています。
新人薬剤師でも、このシートを見れば迷わず疑義照会ができるのです。さらに重要なのは、疑義照会の記録を共有することです。
電子薬歴に疑義照会内容を詳細に記録しておけば、同様のケースが発生した際に即座に対応できます。
疑義照会を効率化する5つのステップ
- 医療機関ごとの連絡先と対応時間を一覧化する
- よくある疑義パターンと回答例をデータベース化する
- 疑義照会の結果を電子薬歴に詳細記録する
- FAXやメールでの疑義照会テンプレートを作成する
- 緊急度の判断基準を明文化する
医師との良好な関係構築も、疑義照会の効率化には欠かせません。日頃から処方傾向を把握し、必要に応じて情報提供を行うことで、信頼関係が生まれます。
信頼関係があれば、疑義照会の回答も迅速になるのです。

ポイント6:服薬指導の「型」を持つ
患者対応の質を保ちながら時間を短縮する技術
服薬指導は薬剤師の専門性が最も発揮される場面です。しかし、丁寧さを追求するあまり、一人あたりの指導時間が長くなりすぎていませんか?
私が経営改善を指導していた薬局で、患者満足度を維持しながら指導時間を短縮したEさんの方法を紹介します。
Eさんは、服薬指導を3つのフェーズに分けて進めていました。
第一フェーズは「安全確認」です。 患者さんの基本情報、アレルギー、併用薬を素早く確認します。第二フェーズは「服薬指導」です。 用法用量、注意事項、副作用の説明を簡潔に行います。第三フェーズは「コミュニケーション」です。 患者さんの困りごとや質問に丁寧に対応します。
この3フェーズを意識することで、指導の漏れがなくなり、かつ時間配分も最適化されるのです。
さらにEさんは、疾患別の服薬指導シートを自作していました。高血圧、糖尿病、脂質異常症など、頻出する疾患については、説明すべきポイントがまとめられています。このシートを頭に入れておくことで、説明が系統立てられ、結果として指導時間が短縮されたのです。
かかりつけ薬剤師として患者さんと継続的に関わる場合、毎回同じ説明を繰り返す必要はありません。
「前回お話しした血圧のお薬ですが、その後いかがですか?」
このように、前回の情報を引き継ぐことで、患者さんとの信頼関係も深まります。服薬指導の効率化は、決して手抜きではありません。 本当に必要な情報に集中し、患者さんにとって価値ある時間を提供することなのです。
ポイント7:チーム全体の業務を「可視化」する
一人で抱え込まない働き方への転換
残業が多い薬剤師の共通点は、業務を一人で抱え込んでいることです。「自分がやった方が早い」という考えは、短期的には正しいかもしれません。 しかし長期的には、あなた自身を疲弊させ、チーム全体の成長を妨げます。
私が推進したのは、業務の可視化と分担です。
ホワイトボードに「今日のタスク一覧」を書き出し、誰が何を担当するか明確にする。 たったこれだけで、チームの生産性は大きく向上しました。薬剤師業務の中には、必ずしも薬剤師でなくても対応できるものがあります。
2019年の厚生労働省通知(いわゆる0402通知)により、薬剤師の管理下において、在庫管理やピッキング、薬袋準備などは、事務員等の非薬剤師が実施可能であることが明確化されました。これらを適切にタスクシフトすることで、薬剤師は対人業務に集中できます。
「薬剤師がやるべきこと」と「事務員に任せられること」を明確に分けることで、薬剤師は専門性の高い業務に集中できます。
| カテゴリ | 薬剤師が集中すべき専門業務 | 事務員(非薬剤師)へ委託可能な業務 |
| 調剤関連 | 処方監査、最終監査、服薬指導 | ピッキング、薬袋・お薬手帳の準備 |
| 在庫管理 | 採用医薬品の決定、期限管理の監督 | 棚卸し補助、検品、自動発注の確認 |
| 事務・IT | 算定項目の最終判断 | レセコン入力、処方箋の整理・スキャン |
| 付随業務 | 疑義照会の判断 | 疑義照会のFAX送信、待ち時間の案内 |
ある薬局では、朝礼で「今日の業務割り振り会議」を5分間実施していました。処方箋の予想枚数、在庫確認の必要性、新薬の情報共有などを確認し、誰が何を担当するか決めるのです。
この習慣により、業務の偏りがなくなり、特定の薬剤師だけが残業する状況が解消されました。
業務分担を成功させる5つのポイント
- 朝礼で当日の業務を全員で確認する
- 薬剤師業務と事務業務を明確に区分する
- 事務員への教育時間を惜しまない
- タスクの進捗状況を可視化する
- 困ったときに助けを求めやすい雰囲気を作る
チームで働くことの本質は、お互いの強みを活かし合うことです。 あなたが全てを背負う必要はありません。
ポイント8:デジタルツールを「活用」する
アナログ業務からの脱却が残業削減の近道
多くの薬局では、いまだに手書きの業務日誌や紙ベースの申し送りが残っています。しかし、デジタルツールを活用することで、これらの業務時間は劇的に短縮できます。
私が過去に導入を支援した薬局では、チャットツールを使った申し送りシステムが大きな効果を上げました。閉局時に次のシフトへの申し送り事項を紙に書くのではなく、グループチャットに投稿するのです。
この方法には3つのメリットがあります。
第一に、申し送り漏れが防げます。 文字として残るため、後から確認できるからです。第二に、書く時間が短縮されます。 スマートフォンでの入力は、手書きより圧倒的に速いのです。第三に、情報共有の範囲が広がります。 休日のスタッフも、チャットを見れば店舗の状況を把握できます。
電子薬歴の機能も、まだ使いこなせていない部分があるはずです。テンプレート機能、音声入力、画像添付、患者さんへのメッセージ送信など、搭載されている機能を最大限活用していますか?
システム会社に問い合わせれば、効率的な使い方を教えてもらえます。 年間の保守料金を払っているのですから、サポートは遠慮なく利用すべきです。
さらに、調剤報酬の算定漏れを防ぐチェックシステムも有効です。電子薬歴と連動した算定チェック機能を使えば、「あ、この加算を取り忘れた」という事態を防げます。デジタル化は難しそうに見えるかもしれません。 しかし一度導入してしまえば、その利便性に驚くはずです。
ポイント9:業務マニュアルを「進化」させる
属人化を排除し、誰でも対応できる体制を作る
残業が発生する大きな要因の一つが、業務の属人化です。
「この業務は○○さんしかできない」という状態は、チーム全体の効率を下げます。
私が取り組んだのは、全業務のマニュアル化でした。調剤手順、在庫管理、疑義照会の進め方、レセプト業務など、全てを文書化したのです。
マニュアルがあれば、新人薬剤師でも迷わず業務を進められます。 ベテラン薬剤師に質問する時間も削減できるのです。しかし、マニュアルは作っただけでは意味がありません。 定期的に見直し、現場の状況に合わせて更新する必要があります。
私が推奨するのは、月に一度の「マニュアル更新会議」です。「このやり方、もっと効率的にできないか?」 「最近トラブルが多いこの業務、手順を見直そう」
こうした議論を通じて、マニュアルは常に進化し続けます。
さらに効果的なのは、動画マニュアルの作成です。スマートフォンで業務の様子を撮影し、音声で説明を加えるだけで、分かりやすいマニュアルが完成します。文字だけでは伝わりにくい調剤の手順や機器の操作方法も、動画なら一目瞭然です。
業務マニュアル作成の5つのコツ
- 誰が読んでも理解できる平易な言葉で書く
- 図や写真を多用して視覚的に分かりやすくする
- よくあるトラブルと対処法を必ず記載する
- 定期的に見直し、現場の声を反映する
- デジタルファイルで管理し、常に最新版にアクセスできるようにする
マニュアル化された業務は、誰でも対応できます。 これが残業削減の大きな武器になるのです。
ポイント10:「やらないこと」を決める勇気
本質的でない業務を手放す決断
最後のポイントは、最も重要かもしれません。それは、やらないことを決める勇気を持つことです。
人事部長としても経営コンサルタントとしても多くの薬局を見てきましたが、残業が多い店舗には共通点がありました。それは、本質的でない業務に時間を奪われているということです。
例えば、過度に丁寧な薬袋の装飾。 例えば、必要以上に詳細な業務記録。 例えば、効果の見えない店舗ミーティング。
これらは本当に必要でしょうか?患者さんの安全と健康に直結する業務以外は、思い切って簡略化するか、やめてしまうことも検討すべきです。
ある薬局では、月に一度「業務断捨離会議」を開催していました。「この業務、本当に必要?」と全ての業務を見直し、不要なものをリストアップする。 そして、店舗全体で「やめる」と決断するのです。この取り組みにより、週5時間の業務時間削減に成功しました。
「もっとちゃんとやらなきゃ」という思いが、あなたを残業に追い込んでいるのです。
業務削減を判断する3つの基準
- 患者さんの安全に直結するか?
- 法的に必須か?
- 費用対効果は適切か?
この3つの基準で判断し、当てはまらない業務は削減を検討すべきです。やることを増やすより、やらないことを決める方が難しい。 しかし、それが残業ゼロへの最短距離なのです。

あなたの時間は、あなたのもの
ここまで、薬剤師の残業ゼロを実現する業務効率化テクニックを10個お伝えしてきました。しかし、これらのテクニックを実践できる環境が、あなたの職場にあるでしょうか?
業務効率化を提案しても「今までのやり方を変えたくない」と拒否される。 システム導入を求めても「予算がない」と却下される。 チーム全体で取り組もうとしても、協力が得られない。
もしそうした環境にいるなら、職場を変えることも選択肢です。
転職を考える際は、「現場のリアルな情報」を持っているエージェントを選んでください。人事として数多くの担当者と対峙し、時に「担当者の固定化」などの厳しい要望を出しても誠実に対応してくれた信頼できる会社は、以下の3社です。紹介会社にとっても「都合の悪い情報(実際の残業時間や離職率)」を包み隠さず教えてくれるかどうかが重要です。

私が人事部長として採用面接を担当していた際、「残業ゼロの実現」を目標に掲げる薬局は確実に増えていました。
働き方改革は、もはや時代の要請です。 優秀な薬剤師を確保するため、多くの薬局が労働環境の改善に本気で取り組んでいるのです。残業が当たり前の環境に甘んじる必要はありません。 業務効率化を実現できる職場は、必ず存在します。
今の環境で悩み続けたあなたを、誰も責めることはできません。 しかし、これからのキャリアは自分で選ぶことができます。残業ゼロの実現は、テクニックだけでなく、環境選びも重要です。 正しい情報を集め、戦略的に行動すれば、理想の働き方は必ず手に入ります。
あなたの時間は、あなたのもの。 その時間を、本当に大切なことに使ってほしい。
人事の現場から率直にお伝えします。もしあなたが「理想の環境」での4月入職を目指すなら、1月に動き出すことには大きな戦略的メリットがあります。
2月・3月は転職市場が最大級に盛り上がり、求人数もピークを迎えますが、同時に「ライバルの数」も爆発的に増える時期です。人事責任者として多くの採用を見てきた経験から言えば、「高年収で、かつ残業が極めて少ない」といった希少な優良枠ほど、比較検討の時間が取れるこの1月のうちに、賢明な薬剤師の方々によって内定が埋まり始めるのが実情です。
混戦となる2月以降にスピード勝負を挑むのも一つの手ですが、今のうちなら、より多くの選択肢の中からじっくりと「自分に合う職場」を見極めることができます。
ただし、焦って「広告費の規模」だけでエージェントを選ばないでください。 私は人事の立場から20社以上の紹介会社と向き合ってきましたが、中には自社の利益を優先し、現場のネガティブな情報を伏せる担当者も少なくありませんでした。
その中で、「現場の離職率や人間関係まで正直に明かし、求職者のキャリアに誠実に向き合ってくれる」と確信できたエージェントは、本当にごく一部です。
納得のいく環境で最高のスタートを4月に迎えるために。私が人事の裏側から見て「ここなら信頼できる」と認定したエージェントと、その賢い活用術をまとめました。一歩先んじて準備を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
あなたの薬剤師としてのキャリアが、より良い方向に進むことを心から願っています。