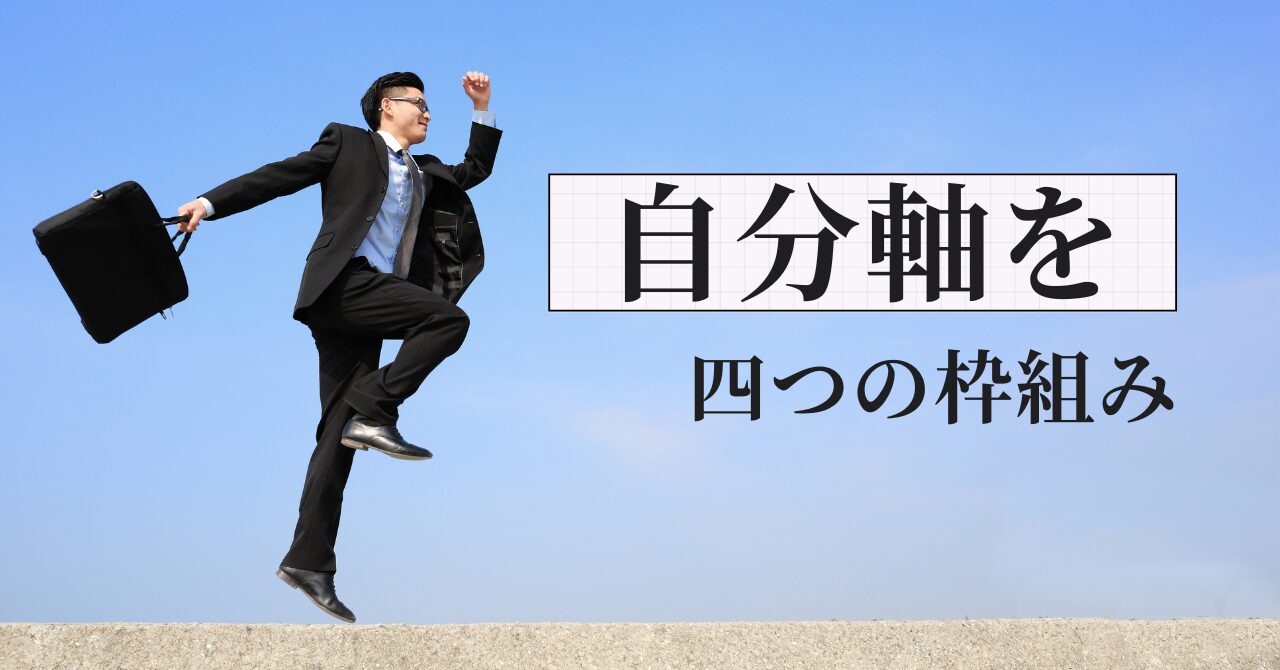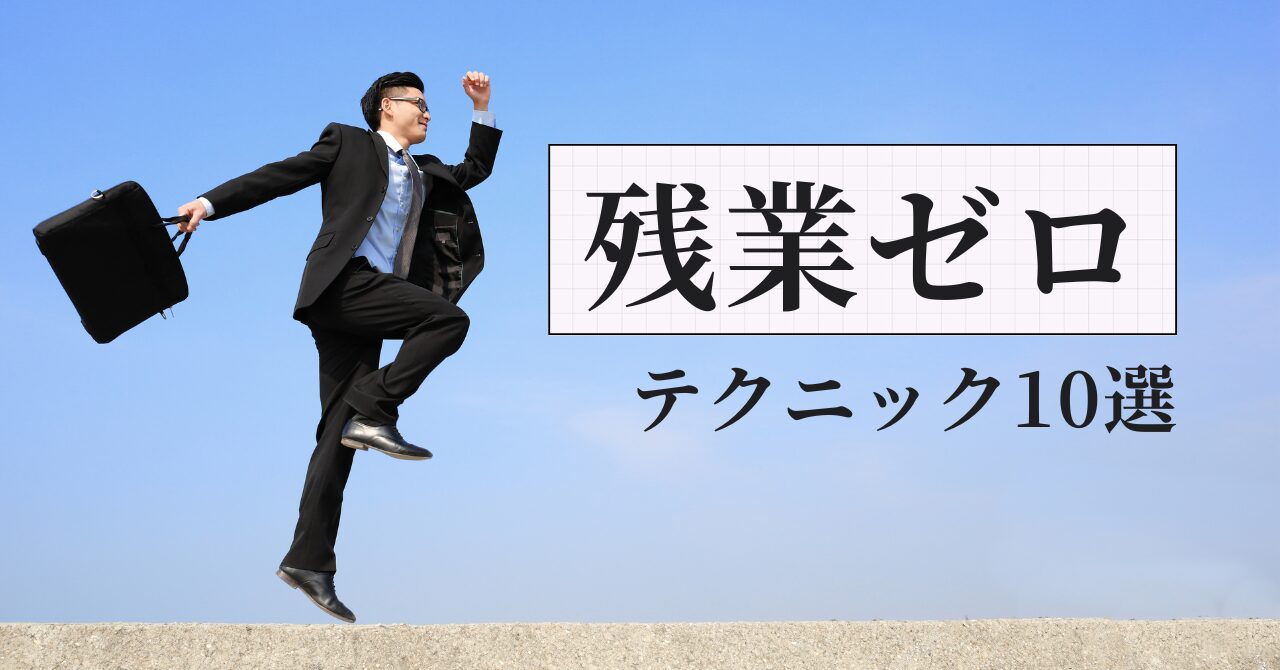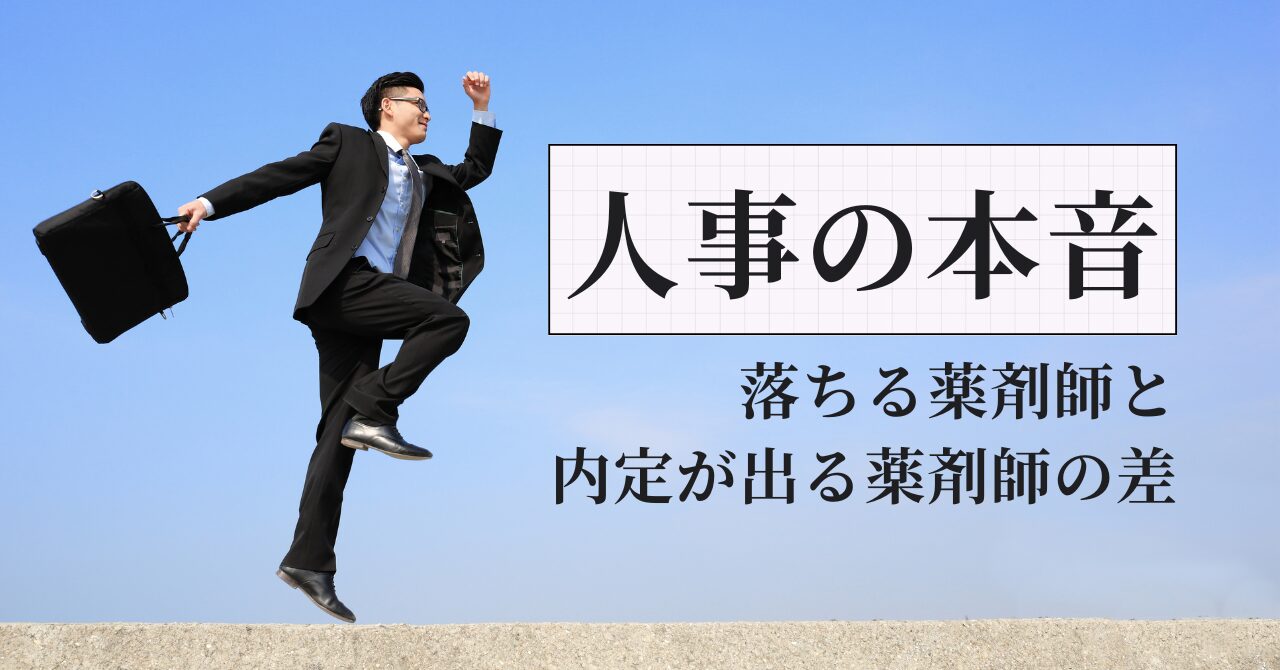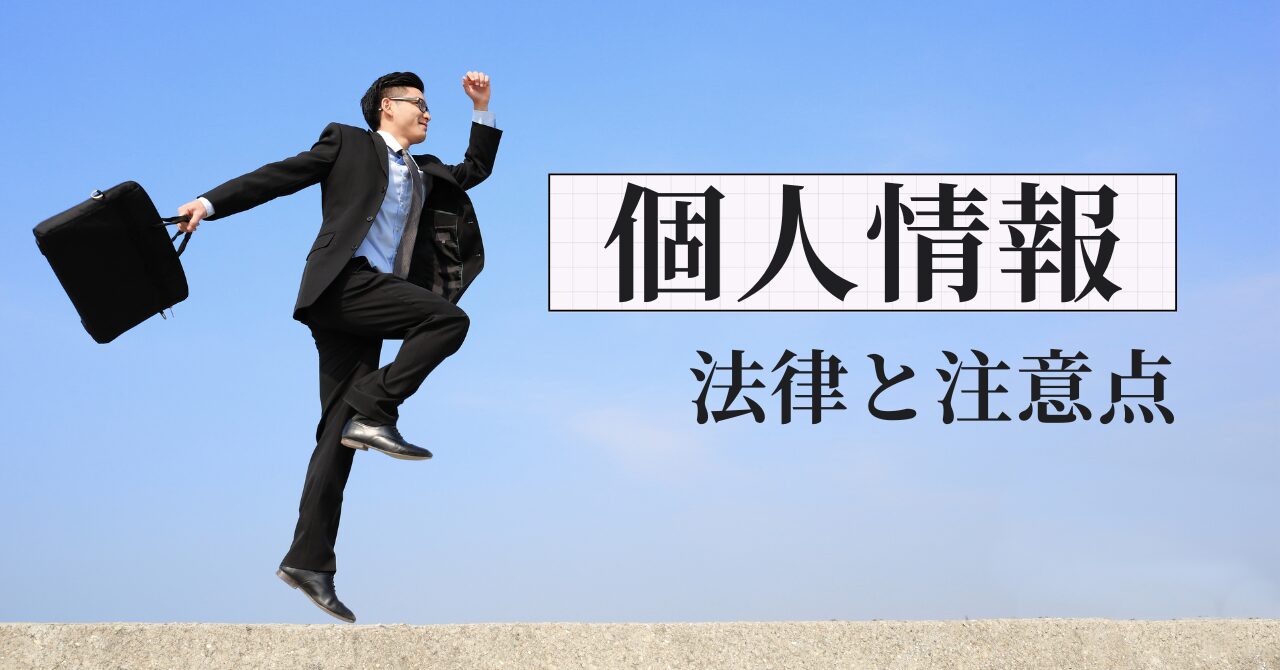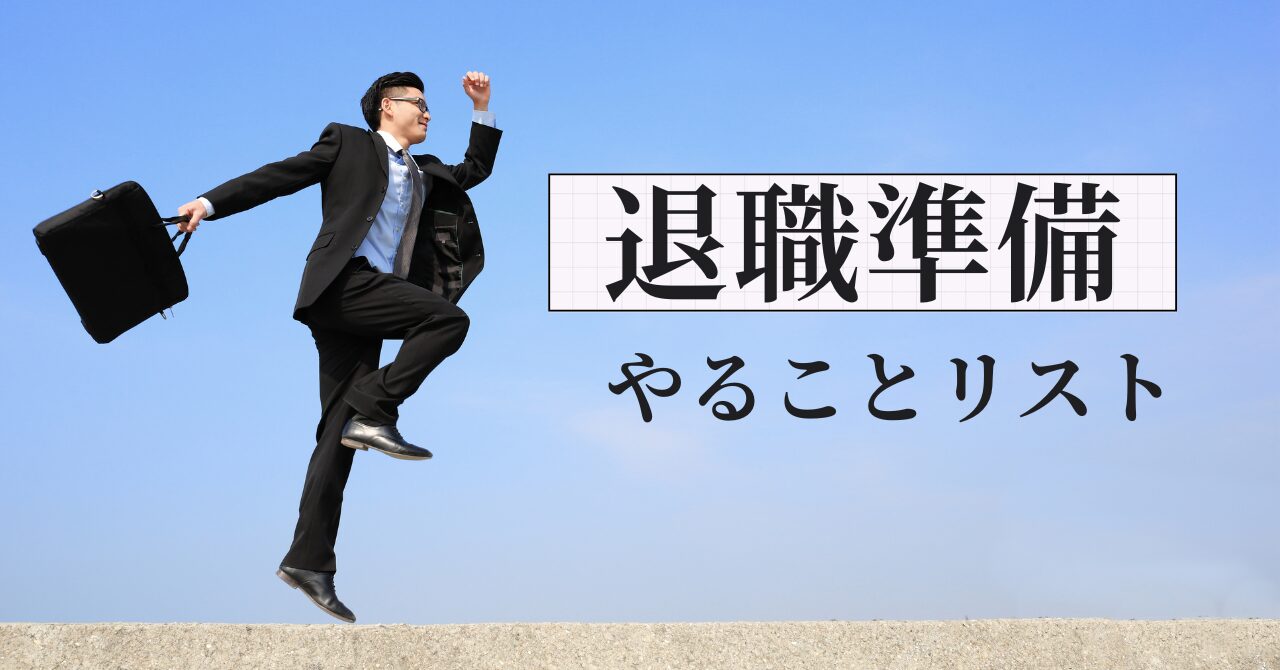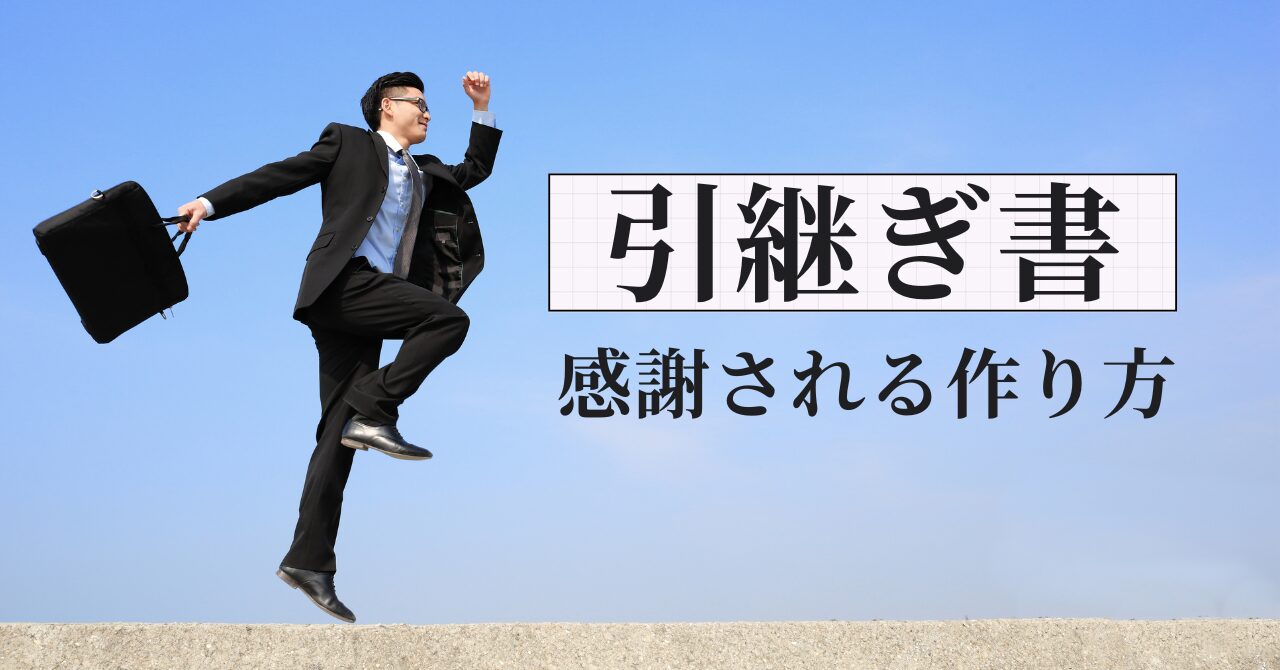※2025年10月時点の情報です
なぜ今、「キャリアの軸」が必要なのか
「このまま今の薬局で働き続けていいのだろうか」 「年収を上げたいけど、何を優先すべきかわからない」 「在宅医療に興味はあるが、本当に自分に向いているのか」
薬剤師としてのキャリアを考えるとき、こうした迷いを抱えている方は少なくありません。
私は元・調剤薬局チェーンの人事部長として、多くの薬剤師のキャリア面談を担当してきました。その中で痛感したのは、「キャリアの軸」が明確な薬剤師ほど、理想の職場を見つけ、長く活躍しているという事実です。
一方で、軸が定まらないまま転職を繰り返す薬剤師も数多く見てきました。年収だけを見て職場を選び、人間関係で悩む。スキルアップを求めて病院に転職したものの、給与の低さに耐えられず再び調剤薬局へ戻る。こうしたミスマッチは、双方にとって不幸な結果を生みます。
本記事では、私の人事部長としての経験と薬剤師資格を持つ立場から、キャリアの方向性に迷ったときに使える実践的なフレームワークを紹介します。このフレームワークを活用すれば、あなた自身の「譲れない価値観」が明確になり、転職活動や今後のキャリア選択において迷いを大幅に減らせるはずです。
「キャリアの軸」とは何か?薬剤師が見失いがちな判断基準
キャリアの軸=あなたの職業人生における「優先順位」
キャリアの軸とは、簡単に言えば「仕事を選ぶ際に、あなたが最も大切にする価値観や条件」のことです。
薬剤師の場合、主な軸は以下の3つに分類できます。
【年収・待遇】
給与水準、福利厚生、昇給制度、賞与などの経済的な要素。
【ワークライフバランス】
勤務時間、休日日数、残業の有無、通勤時間、シフトの柔軟性など。
【専門性・やりがい】
在宅医療、かかりつけ薬剤師、認定薬剤師取得支援、調剤以外の業務(服薬指導の質、地域連携など)。
人事部長として面談をしていると、多くの薬剤師が「全部欲しい」と言います。気持ちはよくわかります。しかし現実には、すべてを同時に満たす職場はほぼ存在しません。
高年収を求めれば激務になる可能性が高く、ワークライフバランスを重視すれば、相場より年収は下がる傾向が一般的です。専門性を追求するなら、認定取得のための自己研鑽の時間が必要です。
軸がないまま転職すると起こること
私の大学時代の知人に、こんな薬剤師がいました。当時30代前半のCさんは「年収を上げたい」という理由で、当時勤めていた調剤薬局から年収50万円アップの条件で転職してきました。
ところが入社3か月後、Cさんは私のもとへ相談に来ました。
「残業が想定以上に多く、家族との時間が取れない」「一人薬剤師のシフトが多く、休憩もまともに取れない」
結局Cさんは、年収アップという「目先の条件」だけで転職先を選び、自分が本当に大切にすべき「家族との時間」を見失っていたのです。
こうしたミスマッチを防ぐために、転職活動を始める前に「自分の軸」を明確にすることが不可欠です。
【コラム】採用担当者は「軸のない人」を3分で見抜く
元人事部長として、正直な話をします。 面接官が最も警戒するのは、「能力が低い人」ではなく「すぐに辞める人」です。そして、早期離職する人の最大の特徴こそが「キャリアの軸がないこと」なのです。
面接で私がよく行う質問があります。
「なぜ、前の職場を辞めたのですか? そして、なぜうちの薬局なのですか?」
軸がない薬剤師は、ここでボロが出ます。
- 「前の職場は残業が多くて…(不満)」
- 「御社は家から近いので…(条件)」
- 「給料が良いと聞いたので…(条件)」
これらはすべて「環境」への依存です。自分の中に判断基準(軸)がないため、環境が変わればまた不満を持ちます。採用担当者はこれを見逃しません。「この人は、また別の不満が出たらすぐに辞めるだろうな」と判断し、不採用(お見送り)にします。
逆に、軸がある人はこう答えます。 「私は在宅医療で患者様の生活を支えたいという軸があります(Will)。前職では外来中心でそれが叶わなかったため転職を決意しました。御社は地域連携に力を入れており、ここでなら私の軸を実現できると考えました」
こう言われると、採用担当者は「この人は目的意識があるから、簡単には辞めない」と確信し、採用に大きく傾きます。 自己分析は、自分のためだけでなく、「選ばれる薬剤師」になるための最強の面接対策でもあるのです。
【フレームワーク1】3つの価値観を点数化する「優先順位マトリックス」
具体的な手順
最初に紹介するのは、シンプルで即効性のある方法です。以下の3つの要素に対して、合計10点になるように点数を振り分けてください。
- 年収・待遇
- ワークライフバランス
- 専門性・やりがい
例えば、「年収4点、ワークライフバランス5点、専門性1点」のように配分します。
この作業を行うだけで、あなたが本当に重視しているものが可視化されます。私の経験上、「頭では年収と言いつつ、実際に点数をつけるとワークライフバランスが最も高い」というケースが意外と多くありました。
点数を基に職場を評価する
次に、現在の職場または転職候補の職場を、同じ3項目で10点満点評価してください。
<例>
現在の職場
- 年収・待遇:3点
- ワークライフバランス:7点
- 専門性・やりがい:2点
転職候補A社
- 年収・待遇:6点
- ワークライフバランス:5点
- 専門性・やりがい:4点
自分の優先順位と職場の評価を照らし合わせることで、「今の職場に留まるべきか」「どの職場が自分に合っているか」が客観的に判断できます。
実際の活用事例
私が支援した40代のDさんは、このマトリックスを使って自分の優先順位を再確認しました。Dさんは当初「年収を上げたい」と話していましたが、点数をつけると「ワークライフバランス6点、年収3点、専門性1点」という結果に。
この気づきをもとに、年収は現状維持でも完全週休2日制と残業ゼロを実現できる職場に転職し、現在は家族との時間を大切にしながら働いています。
【フレームワーク2】過去の経験から探る「モチベーション曲線」分析
モチベーション曲線とは
これは、あなたの薬剤師人生を振り返り、モチベーションの高低を時系列でグラフ化する手法です。横軸に時間(入社1年目、2年目、、)、縦軸にモチベーションの高さ(1〜10点)を取ります。
グラフを描いたら、モチベーションが高かった時期と低かった時期に注目してください。
高かった時期に共通する要素を抽出する
例えば、以下のような質問を自分に投げかけます。
- なぜその時期はモチベーションが高かったのか?
- どんな業務をしていたか?
- どんな人間関係だったか?
- どんな働き方をしていたか?
Eさん(30代女性)の場合、モチベーションが最も高かったのは「在宅医療に携わっていた時期」でした。患者さんやご家族から直接感謝される場面が多く、やりがいを強く感じていたそうです。
一方、モチベーションが低下したのは「処方箋枚数が多すぎて、患者対応が流れ作業になった時期」でした。
この分析により、Eさんは「患者との深い関わりがキャリアの軸」だと気づき、在宅医療に力を入れている薬局への転職を決断しました。
低かった時期から学ぶ「避けるべき環境」
モチベーションが低かった時期の共通点も重要です。それは、あなたが今後避けるべき環境を示しています。
「人間関係が悪かった」「評価制度が不透明だった」「スキルアップの機会がなかった」など、ネガティブな要素をリスト化してください。
転職活動では、これらの要素を持つ職場を事前に排除することで、ミスマッチを防げます。
【フレームワーク3】「Will-Can-Must」で自己分析する
Will-Can-Mustとは
このフレームワークは、ビジネスの世界で広く使われるキャリア分析手法です。以下の3つの円を描き、それぞれに該当する要素を書き出します。
- Will(やりたいこと)
あなたが本当にやりたい業務や実現したいキャリア像。 - Can(できること)
あなたが現時点で持っているスキルや経験。 - Must(求められること)
職場や市場があなたに求めている役割や能力。
この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最も適したキャリアの方向性です。
薬剤師の具体例
具体例として、35歳のFさんのケースを見てみましょう。
Will(やりたいこと)
- 在宅医療で患者さんと深く関わりたい
- 認定薬剤師を取得してスキルアップしたい
Can(できること)
- 調剤業務10年の経験
- 服薬指導に自信がある
- 地域の医療機関とのコミュニケーション能力
Must(求められること)
- 高齢化社会における在宅医療のニーズ拡大
- かかりつけ薬剤師制度の推進
- 地域包括ケアシステムへの参画
Fさんの場合、3つの円が重なる部分は「在宅医療に強い薬局でかかりつけ薬剤師として活躍する」という方向性でした。
この分析をもとに、Fさんは在宅医療に注力している薬局へ転職し、現在は認定薬剤師の取得も視野に入れながら充実したキャリアを歩んでいます。
「Must」を軽視してはいけない理由
多くの薬剤師が「Will」だけを重視し、「Must(市場ニーズ)」を無視してしまいます。しかし、どれだけやりたいことがあっても、市場がそれを求めていない場合、それを仕事として継続・発展させることは難しくなります。
例えば「のんびり働きたい」というWillがあっても、調剤報酬改定により効率化が求められる現場では、その希望は叶いにくいのが現実です。
逆に、市場ニーズに合わせすぎて「Will」を無視すれば、やりがいを失い長続きしません。3つのバランスを取ることが重要です。
【フレームワーク4】転職エージェントを活用した「第三者視点」の導入
なぜ第三者の視点が必要なのか
ここまで紹介した3つのフレームワークは、いずれも自己分析の手法です。しかし、自分だけで分析していると、どうしても主観的な偏りが生じます。
そこで有効なのが、薬剤師専門の転職エージェントを活用することです。
転職エージェントは、あなたの経歴やスキルを客観的に評価し、市場価値を教えてくれます。また、あなたが気づいていない強みや、キャリアの可能性を提示してくれる場合もあります。
私が推奨する3社の活用法
私は人事部長として、多くの転職エージェントと接してきました。その中で、実際に『交渉力が高く、信頼できる』と感じたエージェントについては、以下の記事で実名を挙げて解説しています。
失敗したくない方は、必ずチェックしてください。

エージェントとの面談で必ず聞くべき質問
エージェントと面談する際は、以下の質問を必ず投げかけてください。
- 「私の市場価値は、現在どの程度ですか?」
- 「私のスキルや経験を活かせる職場は、どのような特徴がありますか?」
- 「この求人の実労働時間や退職率は把握していますか?」
これらの質問に対して、具体的なデータや事例を示してくれるエージェントは信頼できます。
逆に、曖昧な回答しか返ってこない場合は、そのエージェントの質を疑うべきです。
複数社に登録するメリット
私は、3社以上のエージェントに登録することを推奨します。理由は以下の通りです。
情報の比較ができる
同じ求人でも、エージェントによって持っている情報量が異なります。複数の視点を得ることで、より正確な判断が可能になります。
交渉力が高まる
複数のエージェントから同じ求人を紹介された場合、条件交渉の余地が生まれます。
相性の良いアドバイザーに出会える
エージェントも人間です。相性の良し悪しがあります。複数社に登録することで、あなたに合ったアドバイザーを見つけられます。
私が人事部長時代、実際に「この担当者は手強い(=候補者のために本気で交渉してくる)」と感じ、信頼関係を築いたエージェントについては、以下の記事で実名を挙げて解説しています。

軸が定まったら、次にすべき3つのアクション
1. 現在の職場で実現可能か検証する
キャリアの軸が明確になったら、まずは現在の職場でその軸を実現できるか確認してください。
例えば、「年収アップ」が軸なら、上司に昇給の可能性を相談する。「ワークライフバランス」が軸なら、シフトの調整や残業削減を交渉する。
転職はリスクを伴いますから、まずは現職での改善可能性を探ることが賢明です。
2. 転職市場の情報を収集する
現職での改善が難しい場合、転職市場の情報収集を始めましょう。
具体的には、先述の薬剤師専門転職エージェントに登録し、以下の情報を集めます。
- 自分の市場価値(年収相場)
- 希望条件に合致する求人の有無
- 求人票に載らないリアルな職場情報(実労働時間、人間関係、経営状態など)
情報収集の段階では、まだ転職を確定させる必要はありません。選択肢を広げるための行動です。
3. 職務経歴書を更新し、面接対策を行う
転職活動を本格化させる場合、職務経歴書の作成と面接対策が必須です。
職務経歴書では、あなたの「軸」に沿った実績やスキルを強調してください。例えば「年収アップ」が軸なら、売上貢献や効率化の実績を記載します。「専門性」が軸なら、認定資格や研修参加歴を詳しく書きます。
面接では、「なぜこの職場を選んだのか」という質問に対して、あなたの軸を明確に説明できるよう準備してください。
私が人事部長として面接を担当していた際、「軸が明確な候補者」は圧倒的に採用率が高かったです。なぜなら、長期的に活躍してくれる可能性が高いと判断できるからです。
キャリアの軸は、あなたの未来を照らす「羅針盤」
ここまで、キャリアの軸を見つけるための4つのフレームワークを紹介してきました。
「優先順位マトリックス」で自分の価値観を数値化する。
「モチベーション曲線」で過去の経験から学ぶ。
「Will-Can-Must」で自己分析と市場ニーズを統合する。
「転職エージェント」で第三者の視点を取り入れる。
これらの手法を実践すれば、あなたのキャリアの軸は必ず見つかります。
私が人事部長として多くの薬剤師と向き合ってきた中で確信しているのは、「軸を持つ薬剤師は、決断に納得感を持っている」ということです。年収、働き方、専門性。どれを選んでも正解です。大切なのは、あなた自身が納得して選択することです。
今の環境で悩み続けたあなたを、誰も責めることはできません。しかし、これから先の未来は、あなたの選択で変えられます。
あなたの市場価値は、現在の環境では適正に評価されていない可能性を秘めています。そのことを、どうか忘れないでください。キャリアの軸が定まれば、次に進むべき道は自然と見えてきます。まずは一歩、行動を起こしてみてください。