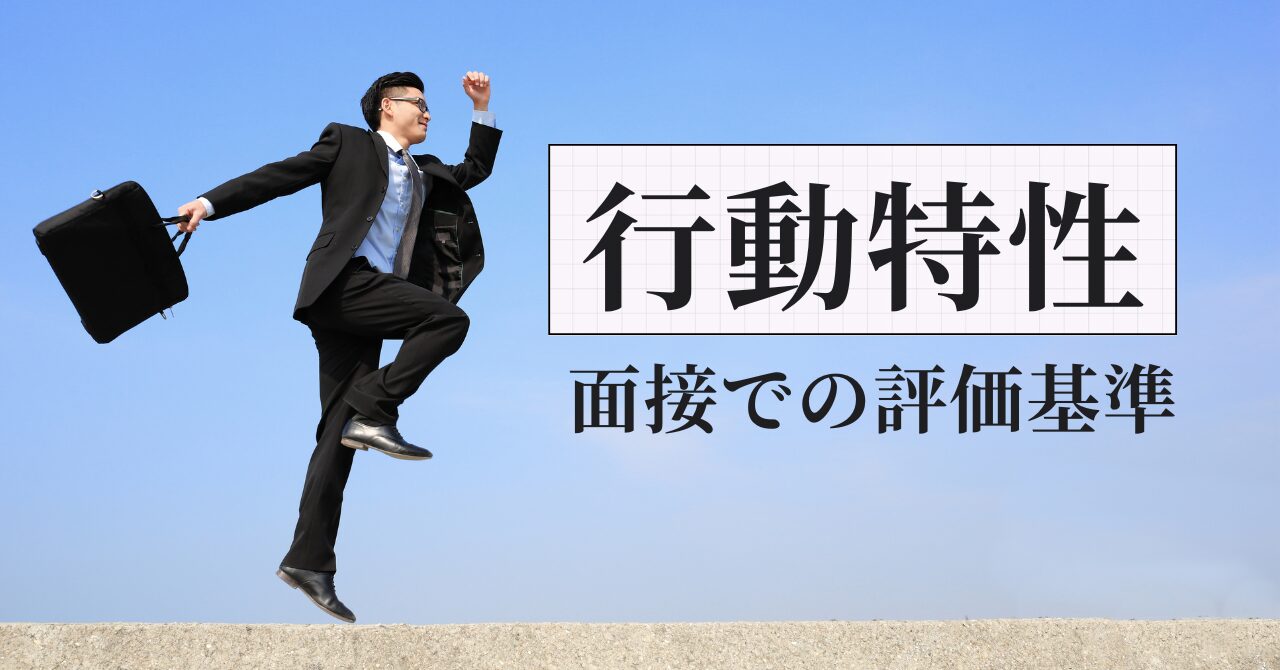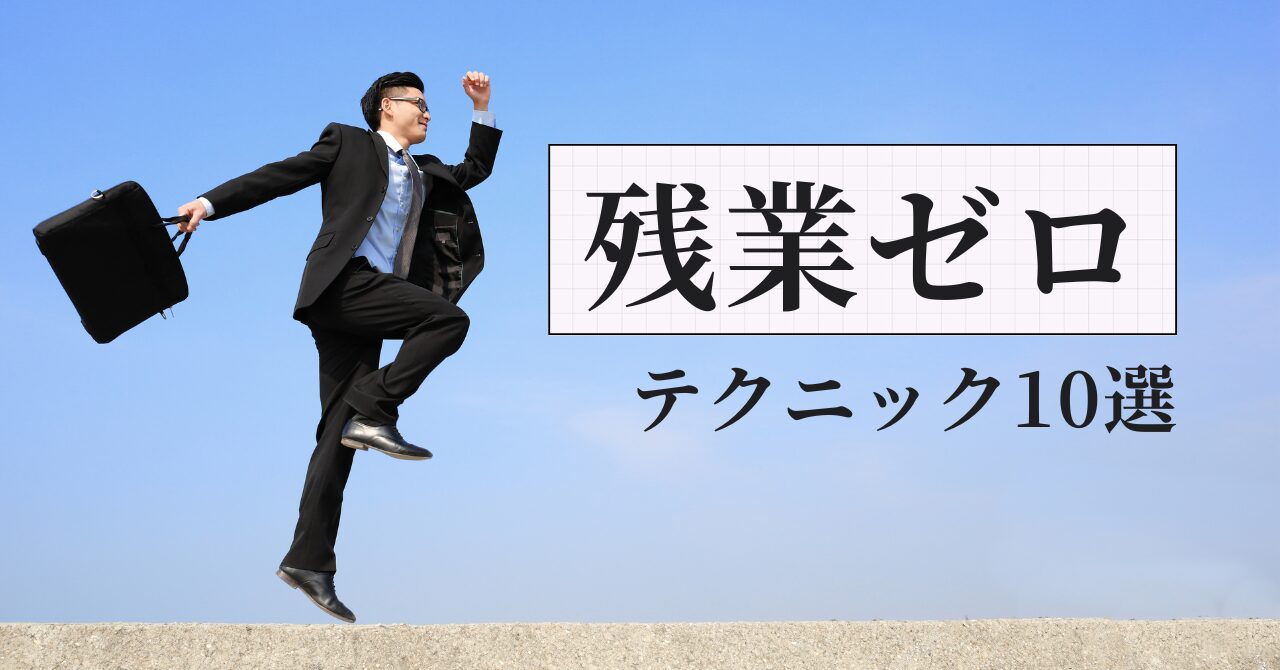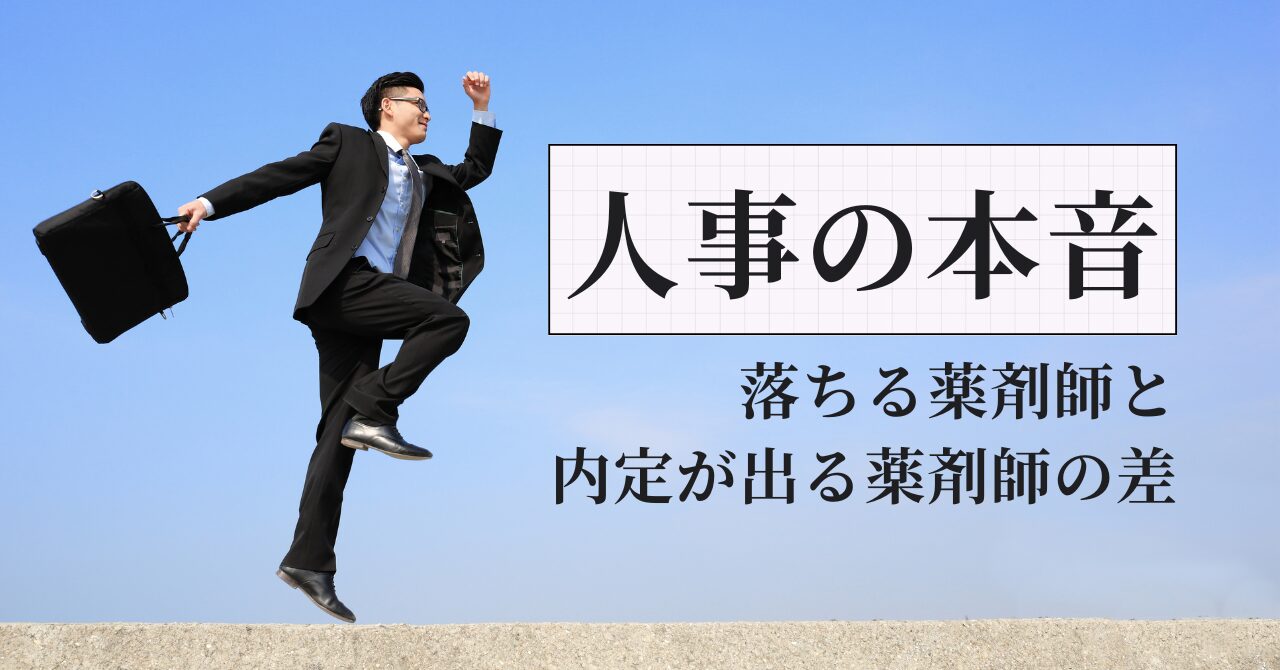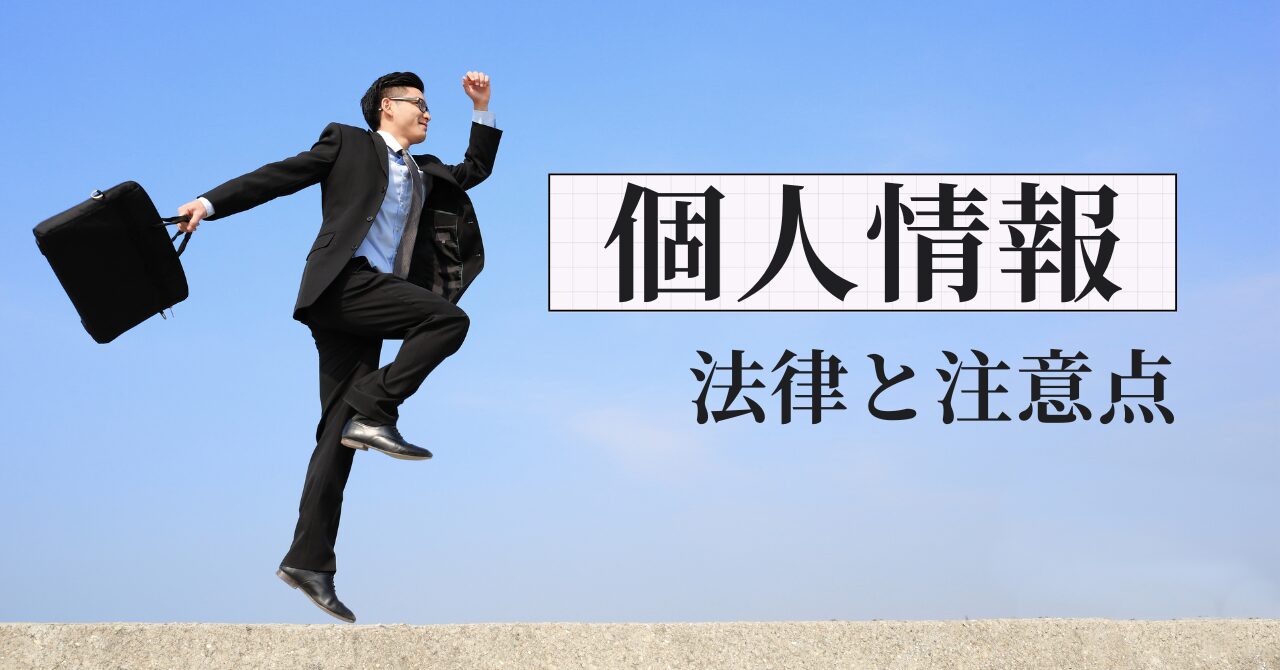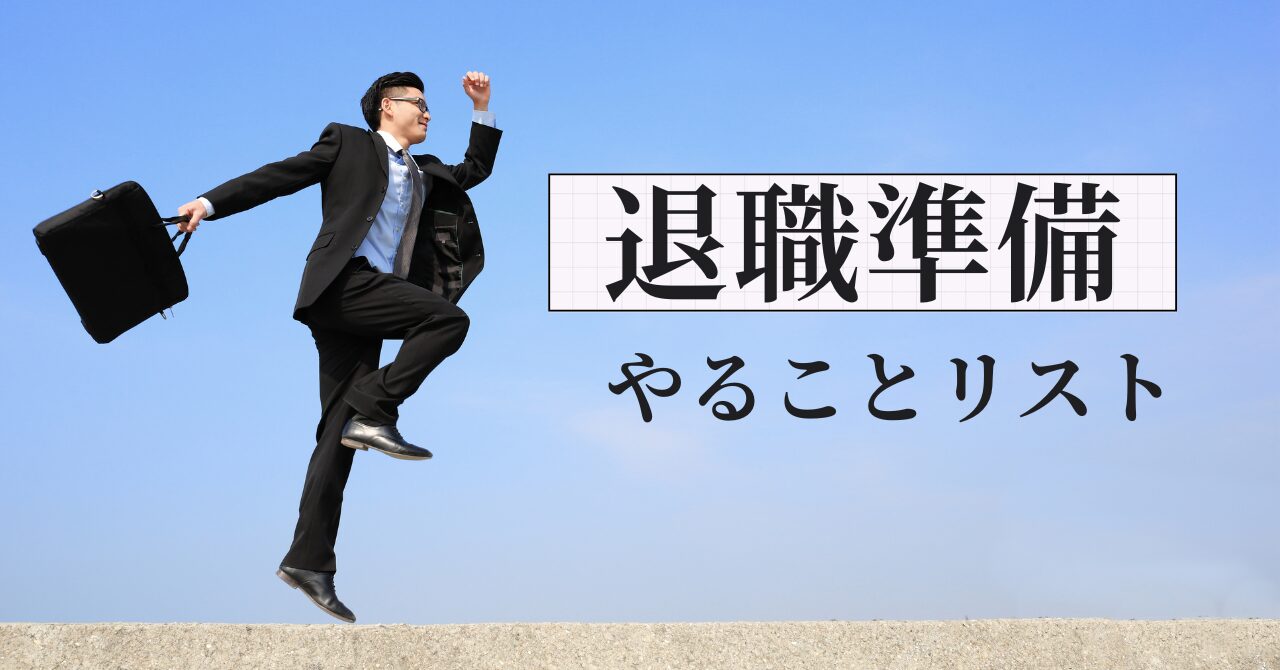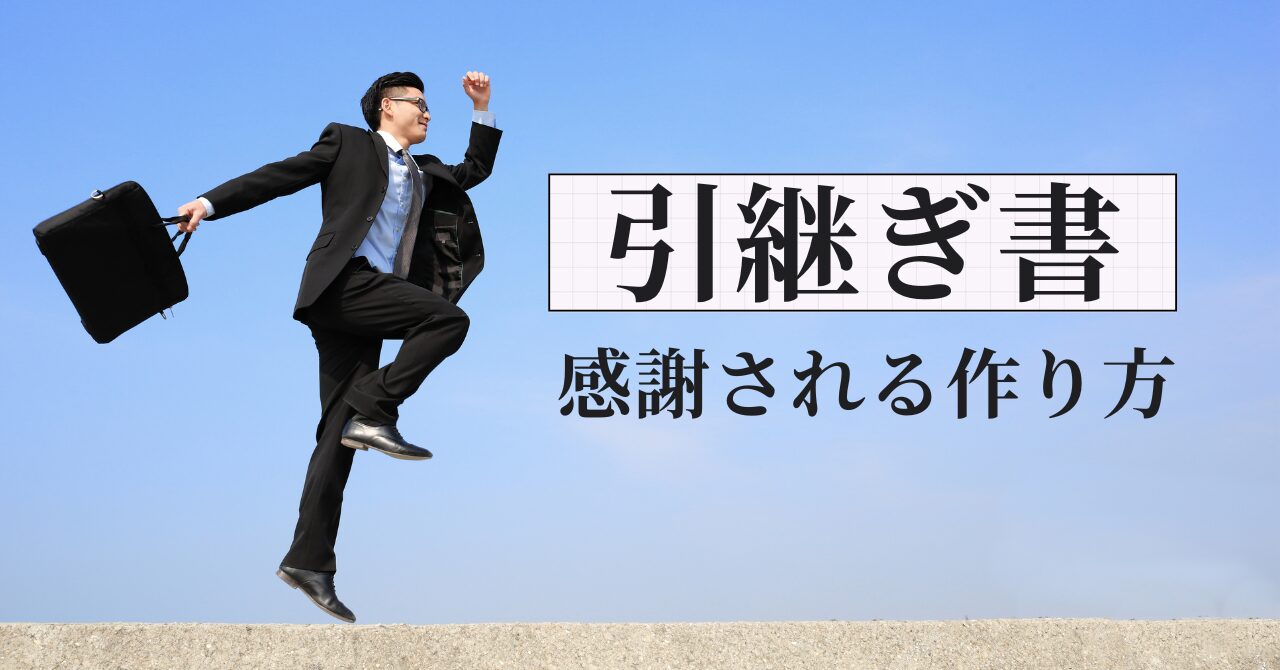2025年10月時点の情報です。
薬剤師の面接で「資格」より「コンピテンシー」が重視される理由
多くの薬剤師は「面接では資格や経歴を詳しく説明すれば受かる」と考えています。
しかし、採用側の視点は全く異なります。採用側が面接で評価しているのは「その薬剤師が『職場でどのような行動をするのか』という行動特性」なのです。この行動特性のことを「コンピテンシー」と呼びます。
コンピテンシーとは「仕事で高い成果を出す人に共通する行動パターン」です。例えば「課題に直面したとき、どのような思考をして、どのような行動をするのか」という点です。単なる「知識」や「資格」ではなく「実際の行動」を指しているのです。
採用側が面接で見ているのは「この薬剤師は『課題に直面したとき、主体的に情報を集め、判断できるのか』」「『ミスが発生したとき、どのように対応するのか』」「『医療機関の医師と『信頼関係を構築できるのか』」といった「行動パターン」なのです。
問題は「多くの薬剤師が『コンピテンシーの概念』を理解していない」という点です。結果として「面接で『何を』答えるべきかが不明確」になり「採用側に『この人の本当の実力は不明だ』という評価」を与えてしまうのです。
採用側の人事担当者は「職務経歴や資格を見れば、その人の『基礎スキル』は判明する」と考えているのです。面接を通じて確認したいのは「『その基礎スキルをどのような場面で、どのように活かすのか』という『行動の現れ方』」なのです。
実務経験として「コンピテンシーを理解して面接に臨む薬剤師」と「資格や経歴のみをアピールする薬剤師」では「採用側の評価に大きな差」が生じるのです。
元・人事部長として「面接で評価されるコンピテンシー」を5つ解説します。これらを理解することで「面接で採用側に『この薬剤師は優秀だ』という確信」を与えることができるのです。
採用側が評価するコンピテンシー
コンピテンシー1:「課題発見・解決能力」
採用側が非常に重視するコンピテンシーの一つが「課題発見・解決能力」です。
つまり「仕事の中で『何か問題がある』と気づき、その原因を追究し、改善方法を実行できるのか」という点です。医療現場では「現状の改善」が常に求められるのです。患者安全、スタッフ効率、医療機関との連携。すべての場面で「より良い方法」が模索されているのです。
採用側が面接でこのコンピテンシーを判定する方法は「過去の具体的な課題解決事例を述べているか」を聴くことです。
悪い回答の例: 「前職では調剤業務が正確でした。患者さんへの説明も丁寧にしていました」
この回答は『やるべきこと』を述べているだけで、工夫や課題解決の事例がありません。採用側には「この薬剤師は『やるべきことをやっている』に過ぎず、『問題を見つけて改善する姿勢がない』」と判断されるのです。
採用側の心理としては「『やるべきことをやる』のは当たり前。その上で『何か工夫をしたのか』が知りたい」というものです。
良い回答の例: 「前職で『患者さんが処方箋を紛失するケースが月5件程度発生』していることに気づきました。原因を医師に相談したところ『医師の説明が不足していた』ことが判明。そこで私が『患者教育用のリーフレットを作成』し、医師と一緒に『説明ステップを統一』しました。結果として『紛失ケースが月1件以下に削減』されました」
この回答は「課題を発見(月5件の紛失)→原因を追究(医師の説明不足)→解決策を実行(教育リーフレット作成と統一)→結果を数値化(削減実績)」という完全な「課題解決プロセス」を示しているのです。
採用側はこの回答から「この薬剤師は『問題に気づき、データを取り、原因分析をし、チームで改善を進める』という高度なスキル」を持つ人材だと判断するのです。さらに「これだけの改善を実行できるなら、うちの薬局での課題解決にも貢献できるだろう」という期待値が生まれるのです。
面接で回答する際の構成は以下の通りです。
- 「課題の具体的な内容」を数字で示す
- 「原因がなぜ生じたのか」を分析する視点を示す
- 「自分がとった行動」を詳細に述べる
- 「実行後の結果」を数値で示す
- 「その経験から学んだこと」を述べる
コンピテンシー2:「チームワーク・リーダーシップ」
医療現場では「個人の力」より「チーム全体の力」が重要です。
採用側が評価するのは「この薬剤師は『医師、看護師、薬局スタッフと協力して、目標を達成できるのか』」という点です。一人で完結する業務はほぼなく、すべてが「他職種との連携」を前提としているのです。
このコンピテンシーを示す方法は「『他者を巻き込んで達成した事例』を述べる」ことです。
悪い回答の例: 「前職では医療機関との関係を構築していました。医師との疑義照会も適切に行っていました」
この回答は「自分の行動のみ」を述べており「チームの力を使ったのか、それとも個人で解決したのか」が不明確です。採用側は「『単なる自分の務めではないか』と判断」するのです。
良い回答の例: 「前職で『医療機関との連携が不十分』という課題があったので『医師との定期ミーティングを提案』しました。初回は医師に『形式的』と感じられていましたが『実際に『患者のための改善案』を持参することで『医師の協力を得られるように』なりました。その結果『3ヶ月後には医師から月平均10件の処方相談を受けるようになり』、患者満足度が向上しました。さらに『看護師からも『薬剤師の意見が参考になる』というコメント』をもらい、医療チーム全体の信頼が構築されました」
この回答は「自分の提案→医師との関係構築→協力体制の形成→他職種への波及→患者満足度向上」という「チーム全体の連携を活かした成果」を示しているのです。
採用側はこの回答から「この薬剤師は『対人スキルが高く、相手を動かし、目標達成ができる人材』」と判断するのです。また「すでに他職種との協力経験がある」ため「うちの薬局でも速やかに『医師や他のスタッフとの信頼関係』を構築するだろう」という期待値が生まれるのです。
コンピテンシー3:「学習意欲・専門性追究」
医療は「常に進化する分野」です。採用側が評価するのは「この薬剤師は『新しい知識を自発的に学び、専門性を高める意欲を持っているのか』」という点です。
医療機関や患者のニーズは毎年変わるのです。「5年前に習った知識」だけでは対応できない場面が連日発生するのです。採用側は「この薬剤師は『変化に対応できるのか』」を見ているのです。
このコンピテンシーを示す方法は「『具体的な学習実績と、それが実務に活かされた事例』を述べる」ことです。
悪い回答の例: 「薬学の知識を深めるために勉強しています。今後も学習を継続したいと思っています」
この回答は「学習『意志』を述べているだけ」で「実績」がありません。採用側は「『本当に実行しているのか』『実務にどう活かされているのか』が不明」と判断するのです。
良い回答の例: 「前職で『在宅医療に関する知識が不足』していることに気づいたので『認定薬剤師資格の取得を目指し』、業務後に『月30時間程度の勉強』を1年間継続しました。資格取得後『月10件の在宅患者指導』を担当するようになり『患者の薬物治療の最適化』に貢献できました。特に『多剤併用患者の薬剤調整』の場面で『自分の学習知識が実務に直結した』ことを実感しました」
この回答は「課題発見→学習計画の立案→実行(月30時間、1年間)→資格取得→実務への活用→患者への具体的な貢献」という「学習が実務に直結している」ことを示しているのです。
採用側はこの回答から「この薬剤師は『自発的に学び、その知識を実務に活かせる人材』」と判断するのです。また「継続的な学習習慣を持っている」ため「今後もキャリアを高め続けるだろう」という将来性も期待できるのです。
コンピテンシー4:「自己認識・改善能力」
自分の『弱点』を認識し、それを改善しようとする姿勢は「長期的な成長を示す指標」です。
採用側が評価するのは「この薬剤師は『自分の不足を認識し、改善する謙虚さを持っているのか』」という点です。完璧な薬剤師は存在しないのです。「自分の課題を認識して、改善する」という姿勢こそが「プロフェッショナル」なのです。
悪い回答の例: 「私の強みは完璧性です。どのような環境でも高いクオリティを保ちます」
この回答は「自分の弱点がない」という主張であり「採用側は『自己認識がない人だ』と判断」するのです。実際には「全員が何らかの課題を持っている」からです。
良い回答の例: 「前職では『新しい提案を進める際に、チーム内の反発に直面する』という課題がありました。その原因は『相手の意見を十分に聴かずに、自分の考えを優先していた』ことに気づきました。その後『提案前に『複数の同僚に意見を聴き、反論を想定して準備する』というプロセスを導入した』結果『提案の承認率が80%から95%に向上しました』。この経験から『コミュニケーション』の重要性を学びました」
この回答は「自分の弱点を認識→原因を分析→改善策を実行→結果を確認」という「自己改善プロセス」を示しているのです。
採用側はこの回答から「この薬剤師は『自分の弱点に向き合い、継続的に改善できる人材』」と判断するのです。
コンピテンシー5:「コミュニケーション能力・共感性」
医療において「人間関係の円滑さ」は、専門知識と同等以上に重要であると言っても過言ではありません。
採用側が評価するのは「この薬剤師は『患者や医療スタッフの『気持ちを理解し、適切に対応できるのか』」という点です。同じ説明をしても「相手の気持ちを理解した説明」と「機械的な説明」では「相手の受け取り方が全く異なる」のです。
悪い回答の例: 「患者さんとのコミュニケーションを大切にしています。わかりやすい説明をしています」
この回答は「意識」を述べているだけで「具体的な事例」がありません。採用側は「『実際に何をしているのか』が不明」と判断するのです。
良い回答の例: 「前職で『高齢患者の多剤併用に関する相談』を受けたとき『医学的な説明だけでは患者が理解できない』ことに気づきました。そこで『患者の生活背景を聴き』『実際に『どのような場面で薬を飲むのか』を確認した上で『日常生活に合わせた『分かりやすい説明方法』を工夫しました。具体的には『朝食後』『夜寝る前』という『時間軸』で整理して説明』したところ『患者の服用率が向上』し『治療効果が改善』されました。さらに『患者が『以前より飲み忘れが減った』と感謝してくれた』ことが、最も大きなやりがいでした」
この回答は「患者の『不理解の原因』を探り→その背景を『共感的に理解』し→患者の『生活に合わせたカスタマイズ』を実施→患者満足度向上」という「相手を理解した上での対応」を示しているのです。
採用側はこの回答から「この薬剤師は『相手の気持ちを理解し、相手に合わせた対応ができる人材』」と判断するのです。
面接で「コンピテンシー」を効果的に伝える方法
面接で「コンピテンシー」を効果的に伝えるためには「事前準備」が不可欠です。
具体的には「職務経歴書に『5つのコンピテンシーを示す事例』を記載しておく」ことです。そうすることで「面接官も『その実例について質問』しやすくなり」、あなた自身も「準備した内容を『自信を持って述べる』」ことができるのです。
各コンピテンシーについて「具体的な数字」「時間軸」「チームの関与」を職務経歴書に記載することが重要なのです。例えば「月5件から月1件へ削減」「1年間、月30時間」「医師と統一」といった「具体性」が「採用側に『この人は実際に行動した』という確信」を与えるのです。
また転職を考える際は、「現場のリアルな情報」を持っている薬剤師転職エージェントをパートナー選んでください。人事として数多くの担当者と対峙し、時に「担当者の固定化」などの厳しい要望を出しても誠実に対応してくれた信頼できる会社は、以下の3社です。エージェントにとっても「都合の悪い情報(実際の残業時間や離職率)」を包み隠さず教えてくれるかどうかが重要です。

さらに「模擬面接」をエージェントに依頼し「実際にコンピテンシーを述べるプラクティス」をすることで「面接当日の緊張が軽減」されるのです。
「コンピテンシーを理解する」ことが面接成功の鍵
薬剤師の面接で受かる人と落ちる人の差は「資格の有無」ではなく「コンピテンシーをいかに効果的に伝えるか」という点です。
5つのコンピテンシー(課題発見・解決、チームワーク、学習意欲、自己認識、コミュニケーション)を理解し「自分の過去の具体的な事例を、コンピテンシーのフレームワークで整理する」ことで「採用側に『この薬剤師は優秀だ』という確信を与える」ことができるのです。
採用側は「資格や経歴から『基礎スキル』を判定」し、面接から「『実際の行動パターン』を判定」しているのです。つまり「面接こそが『本当の評価がされる場』」なのです。
エージェントを活用し「面接対策」を万全にしたうえで「コンピテンシーを意識した回答』を準備してください。その準備が「転職成功への確実な道筋」になるのです。